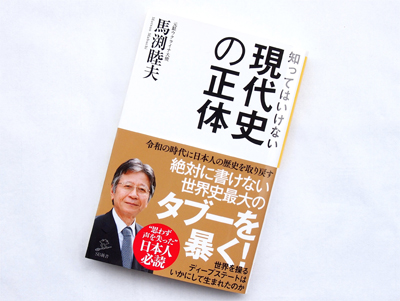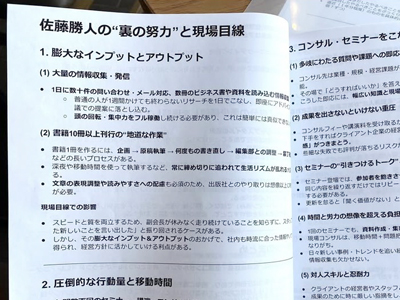「歴史は古代から現代に向けて教わるより現代から逆にさかのぼって教わるほうが今との関連でリアルに学べるのに」というよくある指摘さえまだ知らないまま、当時は教室で大人しく座っていましたが、どの先生たちも一次大戦あたりからは自分の声で、言葉で、授業をせずに済んでいたのは、今思うと半ば意識的にそうしていたのではないでしょうか。
本書は元駐ウクライナ兼モルドバ大使で2008年に外務省を退官後は保守論客の一人として活動を続ける馬渕睦夫氏の最新刊。ネットテレビ局「林原チャンネル」内の番組『ひとりがたり 馬渕睦夫』の内容をもとにした一冊です。新たに書き下ろした「はじめに」には、令和元年5月吉日の日付とともに、アメリカのトランプ大統領が自身の選挙不正疑惑・通称「ロシアゲート疑惑」の捜査に対し全面勝利したことが、本書の内容を象徴する出来事として書かれています。
「現在通説で教えられる世界史は、ロシア革命以降は故意に歪曲されている」「歪曲させた主体がちゃんといて、彼らの力とその利権構造は今も世界を操作している」「ただし、徐々に弱体化はしている。メディアを操作しきれなくなった影響が大きい」――書評はごくごくシンプルに、以上の要約に留めましょう。くだくだしく説明するより、「なんでトランプってあんな変な人の印象になるんだろう」とか、「テレビの報道はみょうに芝居臭くて好きじゃない」と少しでも感じたことがある人なら本書は必読です。なぜそうなるかが書かれているからです。
「なぜそうなるかを問う」という、本書を貫く法論がわかりやすく出た序章の箇所を紹介します。
「1917年の4月にアメリカは大戦に参戦します。同年の11月、イギリスの外務大臣アーサー・バルフォアが、パレスチナ国家建設運動を展開していたユダヤ系貴族院議員の第2代ロスチャイルド男爵ライオネル・ウォルター・ロスチャイルドに対して運動を支持・支援する旨の書簡を送って約束を果たします。/これが有名な「バルフォア宣言」です。学校で使う歴史教科書には、アメリカの参戦やバルフォア宣言、という事象は出てきますが、バルフォア宣言がなぜ出されたか、ということは説明されていません。」(序章「偽りの歴史観」とは p31)
ちなみにこの前後には、時のウィルソン米大統領が不倫をネタにユダヤ系商会の代理人からゆすられており、揉み消すのと引き換えにユダヤ系金融勢力をアメリカの司法のトップの座に入れたことが書かれています。引用中の果たされた「約束」とは、「パレスチナへのユダヤ国家建設にイギリスが同意したらアメリカも第一次世界大戦に参戦すること」という約束=取引です。「なぜそうなるか」まで問うからこそ、こういうことが出てくるのです。
この箇所からは2つの教訓が得られます。一つは、国の行動はこの程度のことでも左右されてしまうということ。メディアと司法と金融をどんな下種なネタででも握れば、大抵のことは操作できてしまう。されてしまうということです。
でももっと重要なのは、人はある事象がカッコつきの「歴史」に属すまではそれを見ないようにしたがる、という教訓ではないか。そうしたがる理由は、好意的に解釈すれば「まだ解釈が定まっていない事柄に自分の臆見を入れたくない」という謙虚さですが、否定的に見ればただの思考停止です。
さらに言えば、私見ではその理由は、この教訓2つを合わせると暗喩的に浮上してくる、「父の権威はどのように担保されるのか」というテーマから来ていると思います。まだ“祖”になりきらない“父”(=「歴史」に属さないものの総称)の権威は問われないことにおいてこそ保たれる。他でもない私たち自身がそれを良しとしているということです。馬渕氏が本書以外でも繰り返しとなえる「精神武装」は、この種の「自明性の罠」にかからないようにすることだと思います。
なお評者から、本書の用語について補足を。51ページ6行目を筆頭に187ページあたりまで続く「国際主義者」(グローバリスト)という用語は、一般へのわかりやすさを優先したまでで、著者の本意ではないと思います。馬渕氏は本当ならInter‐NationalとGlobalを峻別したいはず。「国際主義者」に対応させるなら「インターナショナリスト」をあてたかったはず。なぜそうできなかったかというと、一般向けの訳語が発明される前にGlobalistがとりあえずのカナ書きのままで流通してしまい、あえて日本語(厳密には漢語)で表わすときは「国際主義者」でまかなうしかなくなっているからです。
本来の意味からすればGlobalistは「地球主義者」か「世界主義者」とすべきでしょうが、これだとまるで戦隊シリーズの実写ものに出てくる悪の組織です。あるいは「国際主義」をいったん「各国主義」と近似訳して対の「全国主義者」をあてようにも、日本語で「全国」は通常「日本全国」の意味。先に使われてしまっています。
明治~大正期にかけて欧米の概念が一気に入ってきた当時、夏目漱石をはじめ日本の知識人たちは漢籍の素養を総動員して訳語を発明しました。例えば「存在」も当時できた言葉です。そこから類推すると、現在のカナ言葉の多用は日本人の漢語力が衰えた結果とも考察できます。
こういった裏事情を察することも、「精神武装」の一例のはず。ちなみに、本書の中国関連の内容を読むときは、先に193ページ真ん中の「中国を見る時に忘れてはならない重要な視点3つ」を確認してからが良いと思います。また、日本語の特殊能力であるカナ文化についての解説と、著者が言う「重要な視点3つ」の中身とが一冊で詳しくわかる本として、『中国人と日本人』(邱永漢著・中公文庫)は本書の超お勧めの脇読本。『ひとりがたり 馬渕睦夫』も、番組継続中で過去回も視聴可なので、参考にするとより理解が深まりますよ。