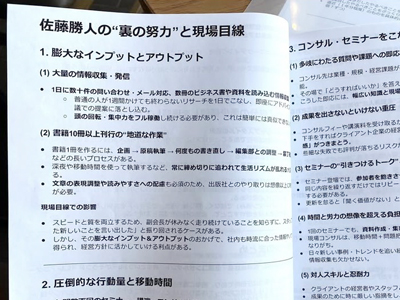「なぜ監査法人は、このような不正を見抜けなかったのか?」 と事件が起きるたびに多くの報道がなされます。また 「不正を知っていたとしても、企業から報酬をもらっているのだから、会社に不利となるような意見を言えるはずがない」 といった指摘をも受けます。
しかし、オリンパスの例では、監査法人側もこの取引が不合理なものと指摘していました。それを受けて会社側は第三者委員会(いわゆる2009年委員会) に意見を徴しましたが、多くの留保条件をおいた不完全な報告書に終わり、監査役会も監査法人もその後の追及を行いませんでした。2011年12月の第三者委員会の報告書がこの点を指摘しているところを見ると、監査役会並びに監査法人側は取引の異常性、不整合、不釣合等の兆候を感じていながらも中途半端な追求になってしまったのかもしれません。
オリンパスの例でも、第三者委員会の調査報告書は要約版15頁で 「“飛ばし” の全貌の発見は困難であったと認められる」 と記述しています。つまり 「そこまでは求められない」 ということでしょう。それほどまでに、極めて複雑な資金の流れとなっていたようなのです。第三者委員会ですら監査の限界を認識している記載ぶりですが、このあたりに、「期待する側とされる側との意識のずれ」――すなわちエクスペクテーションギャップ――が存在しているのです。(そうは言っても、多くの一般の方は、なぜ監査法人は不正を発見できなかったのかと考えます。オリンパス事件については、2011年12月9日付で発表された第三者委員会の調査報告書も詳細に吟味させていただき、「
オリンパス事件の損失分離スキーム」「
損失解消スキーム」として私のブログでコメントしました)。
5、不正事件と監査人の責任
今回の事件の我が業界への影響は計り知れないものがあります。青山学院大学大学院教授の八田進二氏は 「日本の監査は存亡の危機」(経営財務2311114) とさえ言っております。これに対してどう対応すればよいのでしょう?
監査法人の選任権や報酬決定権を監査役に移管する改正案や、監査法人の報酬を被監査会社から貰わない仕組みを作る案も出ていますが、いずれも本質的解決策ではありません。
監査論的には、「監査の本質は二重責任の原則にあるのであって、財務諸表の作成責任は経営者側にあり、監査人は経営者の責任において作成した 『言明書(アサーション)』である財務諸表に対する意見を表明するだけである。」 と考えます。一般の方からすると自己弁護に聞こえるかもしれませんが、むしろこのほうが監査人としての感覚に即しています。私も含め、その立場の監査人たちは 「不適切な会計処理の責任は経営者にある」 という原則を守った上で、 「監査人は監査手続き実施にかかる責任において A:正当な注意を払ったのか B;正当な注意義務を怠ったが、その程度は限定的だったのか C;正当な注意義務を明らかに怠ったのか」 と問おうとします。しかし、このような監査論的な問い方は、一般の方にはその意義と有効性がなかなか理解されません。ジレンマを感じるところです。
6、不正と内部統制実務の変遷
ここで少し、不正会計と監査の関係への取組みが過去から現在に至るまでどのような歴史をたどったかを、上述の八田進二氏の研修会レジュメをもとに、まず米国を中心にふり返ってみます。
・1970年代前半― 経営者は正直であることを前提にして、監査プロセス固有の限界を強調していた。
・1977年― その後、監査人は、専門家としての技術と注意を行使するならば、
通常発見しうるであろう違法行為又は疑わしき行為を摘発することは自らの責任であることを
認識すべきである(1977年「監査基準書」SAS)第17号)とされた。
・1988年― 「監査基準書」SASの大改定で、
「経営者は正直でない」とか「経営者は正直である」との前提をおいてはならないことが強調された。
しかし、その後も米国での不正事件はなくならなかった。
・1996年― 不正を示す用語が 「irregularities(不正行為)」 から 「fraud(詐欺)」 に変更され、
職業専門家としての壊疑心を堅持することの重要性が強調された。
・2002年― エンロン事件後には「財務諸表監査における不正の検討」(SAS第99号)として、
不正のトライアングルの考え方を受け入れて、重要な虚偽の表示が行われる際のリスク要因を分析した。
つまり、A;動機・プレッシャー B;機会 C;姿勢・正当化 の不正のトライアングルが揃ってしまうと
不正が起きるという認識がなされた。
いっぽう日本では、
・2003・2007年― 公認会計士法改正で監査制度の規制強化
・2006年― 「法令違反等事実発見への対応」の新設(金融商品取引法第193条の3)
・2011年9月― 「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応等について」会長通牒平成23年第3号
・2011年12月― 「最近の企業不祥事と監査対応について」会長声明
といった変遷を経てきています。アメリカよりはるかに遅いものの、それなりに考えられてはいるわけですね。しかし事件は起こっています。
7、不正会計処理と今後の課題
内部統制制度による監視機能は、取締役会→内部監査部門→監査役(会)→公認会計士監査と続いて、そのアンカー役を務めるのが外部監査人たる公認会計士監査です。アンカー役である会計監査人は、独立性を堅持しつつ、しかも監査役そして取締役と密接な連携を図って円滑な情報提供を確保しながら業務を進めていかなければなりません。
独立性を更に高めるためには、監査人に対する報酬を会社以外の第三者機関から支払わせるという議論や、監査人に税務当局のような反面調査権を持たせることによって監査の限界を取り除くという議論もありますが、現行の公認会計士監査の本質からしたら、それで問題が解決するというわけではありません 。
有効に機能したコーポレイトガバナンスと内部統制制度のもとに、取締役会・監査役会・監査法人等外部監査人の三者の信頼関係に基づいた良好な監査環境が築かれ、監査法人等の強力な指導性が発揮される監査が行われるようになればと考える次第です。
「オリンパス事件」 や 「大王製紙事件」 が内部統制の枠外の問題となってしまったことの原因は、長年にわたって培われてきた企業風土にあり、そのような風土を生み出す企業文化にこそ求められるべきであったのかもしれません。このような悪しき企業文化を醸成させてしまったのは経営トップの責任でもあります。統制環境の中核に据えられるものは、監査論的に考えても、トップの誠実性や倫理観をおいて他にはないのです。である以上、経営者の 「心の問題」 にまで影響し得るような人間的包容力と影響力が、会計監査人には必要なのかもしれません。
つまりマン・ツー・マンコミュニケーションが重要であり、経営者へのインタビューが重要な監査手続きとなり、「人間観察力」 が監査人自身に問われるのです。最近の若い人中心の監査現場をみると、「マン・トゥー・ディスプレイコミュニケーション」 つまり携帯・スマホ画面でのコミュニケーションばかりが得意で、目と目を合わせたフェイス・トゥー・フェイスのコミュニケーションに欠けているのかと思わざるをえません。
いっぽう、オリンパスを担当した監査人は経営者の交代にまで踏み込んでいます(第三者委員会報告書P185 の12行目参照。PDFは
こちら)。監査業務とは何なのかが、ますます分からなくなってきました。
正月早々、若者への愚痴と、「自らの器を高める」 という極めて困難な問題、そして 「監査業務って何?」 という問題を自分自身で提起してしまい、自己保身的になっているかもしれないと思いつつも、新年に当たって身を引き締める思い再考しています。
執筆者プロフィール
渡辺俊之 Toshiyuki Watanabe
公認会計士・税理士
経 歴
早稲田大学商学部卒業後、監査法人に勤務。昭和50年に独立開業し、渡辺公認会計士事務所を設立。昭和59年に「優和公認会計士共同事務所」を設立発起し、平成6年、理事長に就任(その後、優和会計人グループとして発展し、現在70人が所属)。平成16年には、優和公認会計士共同事務所の仲間と共に「税理士法人優和」(事業所は全国5ヶ所)を設立し、理事長に就任。会計・税務業界の指導者的存在として知られている。東証1部、2部上場会社の社外監査役や地方公共団体の包括外部監査人なども歴任し、幅広く活躍している。主な編著書に『一般・公益 社団・財団法人の実務 ―法務・会計・税務―』(新日本法規出版)がある。
オフィシャルホームページ
http://www.watanabe-cpa.com/