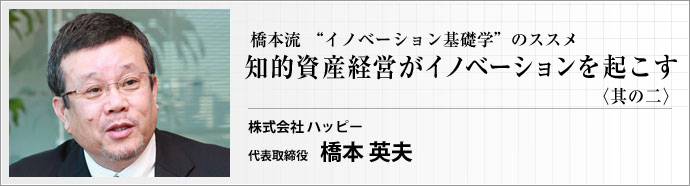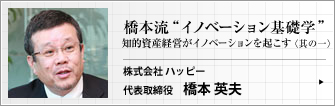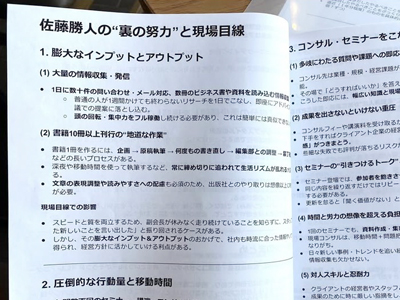「モノからコトへ」 の潮流において 「知的資産経営」 がいかにイノベーションを推し進めるかを説く第四章の2回目。今回は 「ヒューマンプロセスマネジメント」 について詳しく述べる。
イノベーションを起こす本質的要素
社員の持つノウハウは、企業にとって貴重な知識や知恵の結集であり、企業はその知識と知恵によって支えられている。つまり、一人ひとりが地道に積み上げるノウハウは、英知の塊りとなって、他に真似ができないものとなり、また英知を持続的に確保・継続・結集することで、革新=イノベーションを確実なものにすることが可能になる。
知的資産経営では、企業固有のノウハウと社員個人の持つノウハウが密接に繋がったものによって、それぞれ企業のオリジナル商品が作られ、またサービスが提供されていくようでなければならない。
多くの経営者から 「製造業にサービス精神は要らない」 という声を聞くことがあるが、それは大きな誤解である。
モノづくりにもサービスの心がなければ、より良い商品は生み出すことはできない。またモノを売る現場にもサービスがあり、カタチのないものを売るサービス業にはなおのことである。モノにもコトにも “本質的サービスの心” がなければ、次代のビジネスを創造することは不可能と言ってよい。
たとえて、モノづくりのサービスの視点から言えば、トヨタのリコール問題がそれである。マニュアルどおりに作業を消化していれば良しとする効率生産主義から発生している問題であり、あの問題は起こるべくして起きていると言ってよい。
地域性においては使用方法の違いや、その時々に千変万化する人間の心のありようをマニュアルどおりに普遍化されたコンピュータで制御するということは困難であり、設計の段階で折り込んでおかなければ対応は困難だ。
これへの答えは、サービスというカタチのない水面下の、また側面のイレギュラー的な事項を技術品質に反映しなければならないところがある。言わば、五官に感じられない 第六感(勘) のようなものを定量・定性的に置き換える必要がある。
人のココロが感じる 「定量化できないアヤフヤなところ」 で発生した問題であることは確かだが、サービスの根本精神を極めていれば未然に防止できた問題であると言えるだろう。
つまり、「レクサスを高級ブランドに仕立てて販売する/サービスを提供する」 ということをリッツカールトンホテルで学んでカタチは作れても、社員の本質的な精神までは作れなかったのだ。今回のトヨタの問題は、その本質的な精神がモノづくりに生かせなかったということに尽きる。
つまり、それが企業が備えている英知であり、個人が持つ知識と知恵である。それらが企業のノウハウにならなければ企業の永久的存続は不可能だ。
残念なことに、企業が持つ 「人材・組織力・技術・技能・ブランド・顧客とのネットワーク・経営理念・サービスの本質」 などは、財務諸表に表すことができない。
企業の中で長年のあいだに培われたノウハウ、知識や知恵、組織そのもの、技術、技能、本質的サービスなどを生かした経営は 「知的資産経営」 として差別化ができ、市場におけるその企業の絶対的優位を形成する。にもかかわらず、多くの経営者はそのことに気づかない。それらの要素は目に見えにくいからである。しかし、気づかないから放置しておいても良いのか?これには反対者が多いはずである。
実は、財務諸表に表されない 「人材・組織力・技術・技能・ノウハウ・ブランド・顧客とのネットワーク・経営理念・サービスの本質」 こそ知的資産経営の本質的な要素であり、これらは企業がイノベートしていくための基礎・基盤になると言ってよい。
イノベーションを進めるには資金が必要
言葉で説明したり書くことはそう難しくはない。ところが、実際の業務においてイノベーションを起こしていくのは至難のワザである。なぜなら、知的資産という目に見えないもの、すなわち財務諸表に表すことのできないノウハウを創出し、また、それを維持し持続するのは至難のワザといえるからだ。
持続・継続には莫大な資金力が必要となる。資金調達の具体的方策が、経営の重要課題であり、次への戦略ロードマップにおいてのステップで最大のボトルネックとなる。
つまり、財務諸表に表れない知的資産を金融機関が評価することを会計上において認められていない。ところが中小企業は、間接金融に頼らざるをえないことも事実だ。頼らなければならないのに頼る法律がない。金融機関の矛盾がそこにあり、経営を運営していく上において金融機関の貸し渋り、貸しはがしなど、これ以外にも様々に経験をする。
たとえば政権が代わって、返済期間を猶予(モラトリアム)する法律が施工され、資金繰りが楽になったように錯覚する一面があるが、この法律は中小企業にとって一時凌ぎの対応であり、企業が直面する根本解決に繋がるわけではない。
なぜなら、この政策を利用するということは、「私の会社は経営に行き詰まってダメ会社です。倒産寸前です」 と自ら名乗りを上げるようなものだからである。返済できなくなったということは自己破産と同様に受け取られる。したがって「この企業には成長するシーズがない。成長シーズがない企業に資金需要があるとは思えない」こう解釈されるのが至極当然の理解である。
金融機関からすれば、そのような企業は返済能力がなくなったのであり、回収ができなくなる可能性があるという判断がなされる。企業からすれば 「返済猶予をしてもらうほうがよほど恐い」 という笑えない結果になる。
ハッピー 橋本英夫