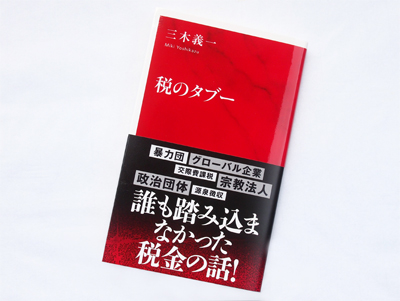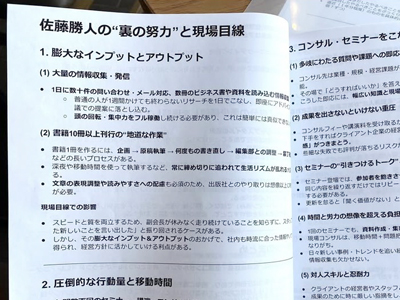読んで思ったのは、当初感じた口調の印象は読者の敷居をとにかく下げるための担当編集者による工夫だったんだろうな、ということと、この工夫――良い意味での偽装――を、著者本人もわかって楽しんでいるな、ということでした。
これらを総合するにつけ、アマゾンレビューで多くの人が言っている「ユーモア」は、評者的にはちょっとニュアンスが違います。より正しくは「諧謔」とすべきでしょう。辞書でひけば洒落も滑稽も機知も諧謔も「ユーモア」ですが、評者としてはカタカナ語の悪い作用で著者の秘めた諧謔を見落とさないようにしたい。
この諧謔味に包んで著者は、よく読むと実は激しい姿勢を本書で貫いています。それは一言でいえばジャーナリズムです。著者の三木義一氏は青山学院大学学長で税法の専門家。つまりアカデミズム畑の人ですが、「まえがき」「あとがき」で次のように言い切るあたり、ジャーナリストの気骨を感じさせます。
「税の世界でタブー視されているものがいくつかあります。それは本当にタブーにしておくべきものでしょうか。‥略‥もしかするとタブー視されている税の問題のほとんどは、タブー扱いされることで利益を得ている人々が誇張して述べているだけなのかもしれないのです。」(まえがき p8)
「本書では、できるだけわかりやすく、反論もされやすいように、明確な主張にするようにしました。「何を言っているのかわからない」ような主張や、反証不能な主張にならないようにしたつもりですので、大いに議論していただければ幸いです。」(あとがき p248)
タブー(禁忌)は自明性の上に成り立ちます。自明性はタブーの成立条件です。だからこそ、「まえがき」の引用はあえて「ところでそれは本当に自明でしょうか?」と言っているわけです。政治家への税優遇を論じた第2章は特にこの筆法が冴える章。「パナマ文書に日本の政治家の名前がなかったのも、日本の議員に世襲議員が多いのも」税で優遇されているせいかもしれない、という34ページの指摘には思わず膝を打ちます。小渕優子議員は父親の小渕恵三元首相から1億2000万円を無税で相続したそうです。
そして「あとがき」の「何を言っているのかわからない」「反証不能な主張」とは、いわゆる官僚コトバが典型的。官僚は――私たちもそうですが――特定の方向で残したい事案があるとき、特に肯定が採決の条件になっていなければ、否定のとっかかりを与えないことに特化した書き方をします。著者はそうしたディフェンス偏重の書き方を意識して避けたと言っているわけです。これらの引用は、本書が発想の仕方と書き方の両方で優れたジャーナリズムの一冊であることを示しています。
読みながら評者は、目次ページの各章に一言ずつ総括コメントをメモしました。以下はその列挙です。
第1章 宗教法人
>> 論を展開するスタイルとスタンスがわかる章
第2章 政治団体と税
>> 教唆的!
第3章 暴力団に課税できるか?
>> 展開がスリリング
第4章 必要経費を考える
>> 所得税の考え方の歴史、からの~「経費とはそもなんぞや?」
第5章 交際費課税はそろそろやめよう
>>「課税・徴税の自己目的化」という課税庁の劣化
第6章 印紙税はいらない!
>> 課税庁と政府の結託、劣化
第7章 固定資産税はミスだらけ
>> ラストで「政治なるもの」の本態が露見する章。地方税の新しい在り方の提議。
第8章 酒の販売と免許
>> 政治の劣化(=有権者の劣化)。議会制民主主義の宿痾。7章と相通じ、おもしろすぎる。このおもしろさが極まれば「政治なるもの」をいぢましく感じる境地に達するか。それまでの展開のドラマ性。ラストでたたみかける筆致の復活。
第9章 特別措置は必要か?
>> 不合理・不条理・不公平の話から、司法裁判制か憲法裁判制かの話になり、吉本隆明が言う「〈アジア的〉ということ」が浮上してきて、最終的に我々一般人の心性の話になる。
第10章 源泉徴収・年末調整
>> ラストが主張してる
最終章 国境
>>水野和夫『資本主義の終焉と歴史の危機』を想起。結局世界は産業革命以来、今もイギリスのものなのか。
上記メモのうち「課税・徴税の自己目的化」「課税庁の劣化」は、一般に組織論で言われるあれです。また「政府の結託」「政治の劣化」に関しては、詩人の鮎川信夫の言葉を思い出しました。一部引用します。
「ところが今はさあ、国家でさえ、なんか予算の問題とかあんなのがほとんどでしょう。あれを見てると、家族の家計のやりくりとものすごく似てるよね。国家的な規模でやりくりをやるわけですよ。国家の関心がほとんど家計の問題になっちゃって、それ以外のことはあまりやっていないね。戦前の国家だったら、そんなことが国家の第一目標じゃあなかったよ。ところが今は、衆議院なんかを見ててもね、もう結局ハウスキーピングとあんまり違わない感じがするけどね。」(思潮社刊『思想と幻想』p94)
鮎川信夫がこう語ったのは今から44年前。1975年です。すでに当時から政治は――議会制民主主義は?――劣化ないし変質していたわけで、今さら何を、という気もしつつ、本書『税のタブー』で著者が一番伝えたかったであろうことが端的に表れている一節をあわせて引いておきます。第4章「必要経費を考える」の90、91ページです。
「こういうと、それじゃ、子育てしているOLが不利になり不合理だ、という議論もあるかもしれません。そうであれば、給与所得者にも、ベビーシッター控除を認めればよいだけの話です。不利に扱われている人たちに合わせて、皆を不利にする発想はやめましょう。」
受け取り方によってはものすごく論議を呼びそうなこのラスト一文が、本書の趣旨の頂点だと思います。この主張のもとに、税制にありがちな「合成の誤謬」の問題も、官僚の「ことなかれ主義」の問題も、政治家の公約が選挙の前後で変わる問題も全部入ってきて、議論されるのを待っている。
ただ、議論して解決に向かうかどうかは第9章へのメモで書いた吉本隆明の「〈アジア的〉ということ」の課題に有権者が一緒に向き合わないと駄目だと思うので、「ほぼ日刊イトイ新聞」運営のサイト「吉本隆明の183講演」から該当の講演をぜひ聞いてほしいと思います。例えば本書の下記の箇所をリンク先のテキスト(講演の一部)と見比べるだけでも、関連が理解できるはずですから。
「日本の裁判制度というのは、後述のヨーロッパのような憲法裁判制度はなく、「司法裁判」制度ですので、具体的に私たちの権利が侵害された場合にしか、ある制度の違憲性を争うことはできません。‥略‥いろいろおかしな優遇措置があるとしても、そのことによってあなたの税負担が過度になっているわけでもなく、あなたの権利義務には何の関係もないですよ、というわけです。/これに対して、ヨーロッパでは、抽象的違憲訴訟というのが認められており、自分に不利な課税がなされるか否かにかかわらず、憲法裁判所で争うことが認められています。」(第9章 p194~196)
消費税増税で税への関心が高まった今、強くお勧めする一冊です。