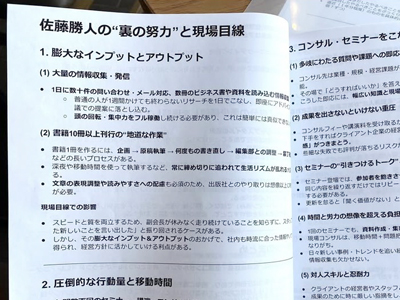「地方自治体が地域ブームを作るために行っている様々な創意工夫も、経済学で解釈してみると違った楽しみ方ができるのではないだろうか。」(p31)
以降、各章や節の最後で、同じ調子の投げかけが折にふれ繰り返されます。つまり本書は、「競争社会でいかに生き抜くか」「どう勝ち抜くか」といった内容の本ではありません。そういったビジネス書的な過激さを期待して読むと肩透かしを食います。そしてもう一度よくタイトルを見ると、『競争社会の歩き方』。散歩や散策のニュアンスです。買ってから「やられた!」と思いました。
でも、そうやってタイトルを勝手に“サバイヴ”のほうに脳内変換していたことに気付いたら、そのときがチャンス。いつのまにか濃い味つけばかりになっていた自身の食習慣ならぬ読書習慣を、一般向け経済学エッセイの“老舗”の味で、ととのえなおしてみてはいかがでしょう。せっかくの食欲の秋、読書の秋ですからね。
本書は2005年の『経済学的思考のセンス』、2010年の『競争と公平感』に続く、経済学の思考法を一般向けに伝えるシリーズの3冊目。著者の大竹文雄氏は名前で説明するより、NHK教育のテレビ番組『オイコノミア』でお笑い芸人の又吉直樹さんと一緒に出演されているあの先生、と言ったほうが通じやすいでしょう。本書にも番組で出た内容がかなり入っているようです。ページ226には「経済情報番組はあっても、経済学教養番組は全くなかったなかで、‥略‥二〇一二年から『オイコノミア』という番組名でレギュラー化され、二〇一七年現在まで六年間も継続している」とあります。「おお、おもしろい番組が始まったな。さすがNHK」と感心した放映開始当時が思い出されますが、あれからはや6年という驚きはさておき、テレビ番組仕込みのわかりやすさは、本書でも健在です。
日本では税は国民が国に納める「義務」を負うものだが、アメリカやドイツ、フランスでは税は国が「権利」として国民に賦課・徴収するものである、とか、日本にもヨーロッパの「public(パブリック)」と似た概念で、かつて村落共同体が一定の山林原野や漁場を共同所有した「入会地(いりあいち)」があるが、日本がヨーロッパと違うのは、publicが国のレベルになった途端に、自分たちとは異なる公があたかも初めから存在していた印象になる、とか、税ひとつとっても経済学者ならではの“目からウロコ”の話が多々出てきます。そんななかで評者が考えさせられたのは、国の投資――財源は税――をめぐって、教育への投資が論じられた箇所でした。
「教育に投資して、イノベーションが生まれれば、私たちはもっと豊かになれる。教育投資によって私たちは将来豊かになれるということが、私たちの共通認識になれば、そのための税を負担することへの抵抗もなくなるのではないか。」(p219)
このくだりを読んだとき、先月取り上げた『「原因と結果」の経済学』を思い出しました。ページ107の、「過去の経済学の研究は、質の高い幼児教育の投資リターンが極めて大きいことを明らかにしているものが多い」という一節。またページ123には、「シカゴ大学のマイケル・グリーンストーンらの研究によると、株式や債券などへの金融投資から得られる平均的な利回りは、大学進学への投資から得られる利回りに遠く及ばず、私たち自身が高度な教育を受けることよりも有利な投資先を見つけることは極めて難しい」とありました。
さらにまた、日本財団が2015年にまとめた『子どもの貧困の社会的損失推計レポート』によれば、生活保護世帯の児童、児童養護施設に在籍する児童、ひとり親世帯の児童らが貧困層ではない一般の児童と同じ割合で高校・大学へ進学し、同じように就職した場合、教育への投資が現状のままの場合に比べて、給与所得者の収入総計が2.9兆円、社会保険料などの納付金が1.1兆円増えるそうです(加藤彰彦著・創英社/三省堂書店刊『貧困児童 ―子どもの貧困からの脱出』p213、214より)。いかに教育への投資が重要かつ有効か、この数字が示しています。ちなみに3~5歳の幼児教育の無償化は7800億円でできるそうです(同p302)。
折しも先月28日に衆議院が解散、今月22日に総選挙が行われます。どの党に票を投じるか、各党の政策を比べる際に経済学的な思考法の端緒でもわかっておくと、これまでと違う判断ができるかもしれません。「public」と「公」の違い、「他店価格対抗」の本当の意味、司馬遼太郎の経済観、所得格差拡大の日米における中身の違い、反競争教育の意外で衝撃的な帰結・・・等々。どれも一読の価値ありです。ご賞味あれ。