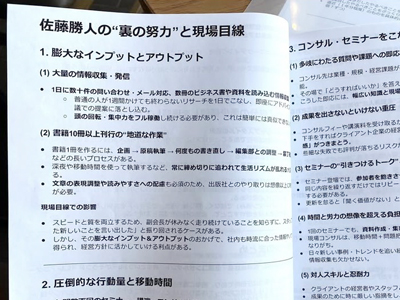記録的な日照不足と2つのトピック

セーラム / PIXTA
これと同じ頃、梅雨寒の空を見上げて“日射量”の不足を嘆いていた一群の人たちがいる。太陽光発電設備のオーナーたちである。太陽光発電(Photovoltaic Power Generation、以降箇所によってPV)は太陽の光エネルギーで発電するので日照時間は必ずしも問題にならないとはいえ、長梅雨となれば日射量も増えず、発電実績は例年に比べ顕著に落ち込まざるを得ない。気象条件に発電能力が左右されるPVの弱点をあらためて知らされた形だった。
一般の人たちとPVオーナーたち。それぞれが同じ空の下で別々の憂いをかこっていたこの時期に、太陽光発電をめぐっては2つのトピックが進行していた。一つは、再エネ発電による余剰電力の固定価格買取制度(FIT)が終了し始める10月を間近にひかえ、電力各社(東京電力や関西電力などの旧大手10社および電気事業法改正以降のいわゆる新電力)が自社の買取価格をあいついで発表した動き。そしてもう一つは、経産省と資源エネルギー庁が進める「地域分散型電源活用モデル事業」に関する具体的な動きである。
蓄電池等補助金事業の公募
ただ、だからといって卒FIT後は投資=売電型の運用を全部止めて自家消費に閉じこもるよう促すのも違うだろう。行政的には下策でもある。今まで制度でゲタを履かせて市場相場より高くPV電力を買ってきたのは、一般の人たちから再エネ賦課金として集めた資金をPVオーナーに優先的に投資していたのであり、政策的には社会資本投資の一種だからだ。投資は回収すれば終わりではない。実を結ぶまでが投資である。
そしてこの文脈で、以前取り上げたときは脇においたテーマ――「地域分散型電源システムの確立」――が浮上してくる。先のトピック2つのうち、「地域分散型電源活用モデル事業」がそれだ。長梅雨の間に進んでいたその具体的な動きとは、一連の「災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金」の公募受付である。
PVオーナーたちのコモンセンス
むやみに“べき論”で語りたくはないが、社会の投資を受けて太陽光発電を導入した以上、PVオーナーは自己投資ぶんを回収した後も自家消費に留まることなく、できるだけ地域マイクログリッドに参加してくれることを願いたい。余剰電力を系統配電線(グリッド)に供給して、各自治体が目指す電力資源の自立に協力できるようになってほしい。
あるいはそんな“べき論”をかざすまでもなく、一般のPVオーナーつまり10kw未満の低圧PV発電家には、いざとなればそういったコモンセンスを発揮する人がそもそも多いのではないか。これはグリッドに接続した例ではないが、2016年4月の熊本大震災の際は避難者が持ち込んだプラグインハイブリッドカー(PHEV)が避難所の非常電源代りとなって他の避難者たちを助けた。このPHEV――三菱自動車のアウトランダー――の蓄電池容量は12kwhで、普段の生活をまかなうぶんには標準世帯が1日使えば終わりだが、ガソリン満タンでエンジンを回して発電しながらであれば10日持つという。避難生活中の非常電源として頼るぶんにはいかに心強かったか、避難者たちの心中は察するに余りある。
「自給自足」と「地域経済循環」のへだたり
いっぽうで、石川県加賀市のように地域マイクログリッドに前のめりな自治体は、買える再エネは何でも買う構えのようだ。日経エネルギーNextの記事(「日本初の自治体100%出資、加賀市が新電力をスタート」)には、「加賀市内から100憶円以上のお金が電気料金として北陸電力がある富山市に流出している。自治体新電力を手掛けることで流出を止め、地域経済循環を作りたいという思いがあった」という、宮元陸市長の切実な言葉がつづられている。同様の悩みと願いを抱える自治体は列島各地に数えきれないほどあるはずだ。
バーチャルパワープラントへの期待
制度面についてはこれから、特にバーチャルパワープラント(VPP)が実証段階を経て社会実装されていくなかでさまざまな整備が進むのではないか。バーチャルパワープラントとは、従来のように大規模集中型電源(=発電所)の供給調整だけで電力を安定させるのではなく需要側も自然に需給両面を制御するようになることで全体として安定電源を確保し、仮想発電所のように機能しようという発想だ。直近で3月下旬に行われた「平成30年度需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金成果報告会」の資料からは、参加企業によって問題点の洗い出しが具体的に進んでいる様子がうかがえる。
そういえば長梅雨のあいだに参議院議員選挙もあった。国政の変化いかんに関わらず、引き続き関連施策が推進されることを願う。
(ライター 筒井秀礼)
(2019.8.7)