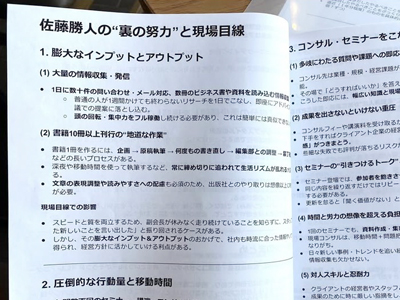しかしこの頃にはもう、「朝何時に起きて途中何と何を買って何時にはどこそこに着いて、買い出し班を率いて何時頃には買い物を終えて現地に向かい始めて・・・」と明日の行動がイメージできているのは、本書が言う「悲観する力」で考え切ったからだと思います。そうして至った無味乾燥の境地とはつまるところ、「これで最低限の期待は実現される」という確信と引き換えに得る余裕であり、そう思うとおよそ「余裕」とか「自然体」とかいうものは、本人には随分と味気ないもののようです。
本書は工学博士で作家の森博嗣氏の最新刊。『すべてがFになる』でデビュー以降、小説の他に一般書も17冊出しているとのことで、小欄でも3年前に『作家の収支』を取り上げました(vol.21)。狙った抑揚がどこにもない、フラットでニュートラルな筆致で、かえってそれが事実の盛り上がりを際立たせる文体は本書でも健在です。
ただ、著者自身が「本書に書かれている内容は、かつては常識的なことであり、誰もが知っている当たり前の考え方、人間の生き方だったのではないか」とまえがきで断わっているように、本書の内容そのものは、あるレベル以上の読者にとっては全体的に一般論の印象を禁じ得ない気がします。人の感情や心の動きに関する箇所にいたっては暴論と言えるぐらい粗い印象を感じる箇所もあります。とはいえこの点に関しても、自殺を考えている人について「僕が言えるとしたら」と前置きして語った内容に関してと同様、著者は独特の流儀で「僕には関係がないことだ」(p172)とおっしゃるのでしょう。
客観的な事実を材として読者とある種の世界観を共有する本――『作家の収支』が一例でしょう――は別として、このスタンスがどうにも受け付けない読者は一定数いそうです。一方でそのスタンスのぶれなさ――内容ではなくスタンスのぶれなさ――をおもしろがって、いわば“消費”するように読む読者と、そういう読まれ方を見込んで依頼する出版社はありそうな気がします。なんだか寂しいですが、「それのどこが問題なの?」と当の著者自身がおっしゃりそうな気がするのは、書評子の悲観でしょうか。第3章には次のような一節があるのですが。
「それでも、ときどき、「ちょっと、これはどうなのか?」という引っかかりが訪れるはずだ。人間関係の問題や、職場での釈然としない出来事に溜息をつくとき、あるいは流れに乗っているだけの虚しさみたいなものを感じたときなどである。‥略‥なにかの切っ掛けでふと孤独を感じたときに、なんとなく、湧き上がってくる寂しさのようなものがある。‥略‥そんなときに、「このままで良いのか?」という小さな「悲観」が生まれることがある。」(第3章 正面から積極的に悲観する p104)
引用は著者が「かなり抽象的」とあらかじめ断る本書のなかでもとりわけ抽象的な一節。悲観することの意義を「思い通りにならなかった場合を想定して備えるようになる」という実用面の効能に矮小化せず、もう1つ上の次元に展開した数少ない箇所です。本書が一貫して主張するのは、悲観こそ「考える」という知的活動の源泉だということ。引用はワンセンテンスはさんで「流れに乗ったつもりでも、ときどき訪れる、ちょっとした違和感が、実は「考える」チャンスなのである」と続きます。次のページには「すなわち、心配が思考の起源なのではないだろうか」とあります。175ページでは「未来を「悲観」すれば、少なくとも考え続ける人間にはなれる」と書きます。極めつけは楽観との対比で語られる次の一節。略さず引用します。
「そもそも、楽観のメリットは、「考えない」という省エネなのだ。考えることは、つまり悩むことと等しく、限りなく「悲観」に近い活動である。頭脳を使うことは大きなエネルギィ消費であり、生物としても、できるだけ考えない方向へ進化しようとしているのが、現在の人類だろう。/もともと、人は考えたくなかったから集団を形成し、大勢でリスクを分散して、誰かが気づけばみんなで活動する、という体制、すなわち社会を築いた。個人の生活では、考えることが多すぎて、面倒この上ないからだ。人間は、社会的になることで、考えなくても済むようになった。」(第2章 あまりにも楽観的な人々 p78,79)。
この指摘を本書が言う意味で悲観するとしたら、「誰かが気づけばみんなで活動する、という体制」は容易に「誰かが気づくだろう」という楽観に転化するだろう、ということになりそうです。結果、誰もが活動をしなくなる。結果、社会は均質化し停滞する。“個”が集団化・社会化するにつれ「考えること」=「悲観」を忘れていく様は、熱力学第二法則(エントロピー増大則)さながらです。
そして今、評者の目下の気がかりは、「考え抜いたつもりが気付けていない明日の花見の実現不可能性に他の誰かが気付いて対策を講じてくれているだろうか」です。「実現不可能性」は厳密には「期待の実現不可能性」なので、自分の期待値を下げればいいのでしょうが・・・ちょっとそれは、したくないですね。