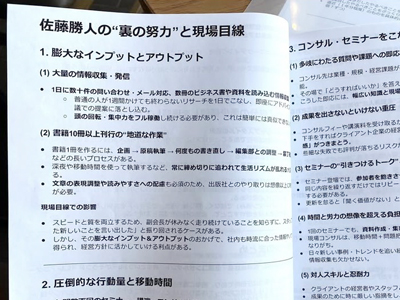人類史上未曽有の出来事
SDGsは「エスディージーズ」と読む。正式名は「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」。2001年に国連で採択されてから世界的に取り組みが進んできた「MDGs(ミレニアム開発目標)」の後継として、さらにはこの10数年における世界情勢の変化――途上国の低・中所得国化、多国間関係のさらなる複雑化、産業経済の進展に伴う新たな諸問題の台頭、気候変動等――を受けて2015年に採択された国際協調の枠組みだ。達成期限は2030年。それまでに、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で定めた17の目標と169のターゲットを達成するべく、各国が取り組みを行う。
このSDGs、実は民間企業にも大いに関係がある。一つには、MDGsが途上国向けの開発目標だったのに対し、SDGsは193の全加盟国が対象であること。これはとりもなおさず、世界中の国や地域、社会の未開拓なニーズにSDGsという共通フォーマットが引かれたことを意味する。また、国連内の専門家が主導したMDGsと違い、SDGsは各国の政府、民間企業、NGO団体等を活動主体に想定している。アジェンダは次のように明記する。
「民間企業の活動・投資・イノベーションは、生産性及び包摂的な経済成長と雇用創出を生み出していく上での重要な鍵である。我々は、小企業から協同組合、多国籍企業までを包摂する民間セクターの多様性を認める。我々は、こうした民間セクターに対し、持続可能な開発目標における課題解決のための創造性とイノベーションを発揮することを求める。」(第67条)
ナイーブな前後段の間にある「我々は~多様性を認める」のくだりに注目すべきだ。条文は「関連法を遵守し、国際的に定められた最低基準を維持し、普遍的な権利を尊重する責任」(企業向け導入ガイド『SDG Compass』p8より)に対処するなら、様々な形で民間の営利企業が入ってくるのを拒まないと言っているのだ。むしろ、技術力、企画開発力、業務ノウハウといった民間企業のリソースは市場という競争環境でつちかわれてきたからこその生産性と効率を備えており、それに期待する、と言っている。
産業革命以降、企業の営利活動はしばしば人類の高邁な理想――人権の尊重、健康福祉の増進、普遍教育の普及等――とトレード・オフの関係にあった。企業は営利を追求し、それを政府が法令や規制でしばり、妥協点で成立してきたのがこれまでの産業経済のいつわらざる姿だった。それが少なくとも2030年までは、共存発展する道を探るところに両者の関係が収斂していくことが全世界規模で約束されたのだ。これは未曽有の出来事である。
SDGsはCSRよりもCSVに位置付けよ
日本企業が巻き返す策はあるだろうか。CSR(企業の社会的責任)に代わって言われるようになったCSVの考え方が、その参考になりそうだ。
CSVは2011年にハーバードビジネススクールのマイケル・E・ポーター教授が論文『Creating Shared Value』(邦題『経済的価値と社会的価値を同時実現する共通価値の戦略』)で提唱した、企業のための差別化戦略である。ポーター教授によれば、「寄付や社会貢献を通じて自社イメージの向上を図る従来のCSRは、ビジネスとの相関性はほとんどない」。それよりも、自社の持つ強み(経営資源・専門性等)を活かしてビジネスとして社会問題を解決したほうが効果がある。先進地域で取り組む際はこちらが主になるかもしれない。
企業と社会の協働が求められる
そこで提案だが、SDGsを中間管理職の専管事項にしてはどうか。抽象的・概念的なCSRと違い、自分で経験して取り組んで“自分事”にしないと意義がわかりにくいのがSDGsだ。幸いにも「経営陣に定着している」は28%と、一昨年から8%伸びている。経営者がSDGsを「社運を左右する経営戦略=CSV」と明確に位置づけ、末端の担当職ではなく中間管理職に自ら取り組ませれば、状況は変わるのではないか。
その際の資料やツールとしては、先の『Compass』『Industry Matrix』『動き出したSDGsとビジネス』が使えるだろう。そもそもSDGsは「これからのニーズはどこにあるか」という、企業が一番知りたいことを示したものだ。日本企業の多くがそれにとどまるという「既存の企業理念や事業との整合性を判断するためのチェックリスト、いわゆる棚卸し」として活用するだけではもったいない。
また、社会の側の理解も不可欠だ。ファストファッション産業の労働者搾取問題をきっかけに知られるようになった「エシカル消費」はその端緒になるだろうか。他にも、おそらく2020年には東京オリンピックを機に、欧米諸国に比べ遅れている日本の畜産動物の扱い(例;採卵鶏のバタリーケージ)が世界に知られ、畜産業界と消費者はともに見直しを迫られる。これもSDGsについて考える端緒になるだろう。
2030年まで待ったなし。企業と社会の協働が求められる。
(2017.11.08)