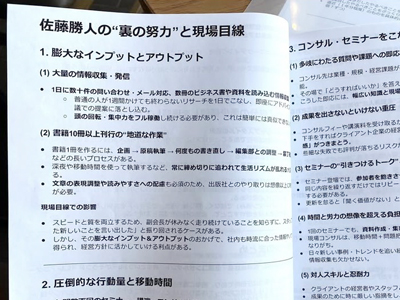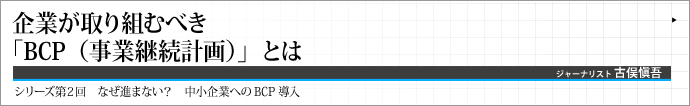陽の当たる道に至る成長秘話
おのれを育て上げる葛藤と素養とは

これじゃいけないんじゃないか、こういう思いでお客さんの前に立ってしまっては失礼なんじゃないか。もしかしたら‥‥俺は、今まで培ったものを全部捨てても、ゼロから勝負をしなくてはいけないんじゃないか‥‥。
そんなとき、隣には必ず (岸谷) 五朗がいたんです。五朗は、本当に不思議な縁を感じる男です。彼のほうがSETの1年先輩なんですが、入団して初日から 「こいつとは一生の付き合いになるな」 と思ったほど。なぜだか五朗とは考えていることがことごとく同じだったので、意気投合するのにも時間はほとんどかかりませんでした。
劇団について悶々と考えている時期、五朗の運転で移動していたことがあったんですね。車内ではどちらも話をせず、ずっと黙っていた。でもお互いに考えていることは同じでした。五朗が一言、「どうする?」 と言う。「そうなんだよな、そういう時期かもな」。ドラマのような話ですが、これだけで理解しあえていました。それが次へと踏み出すスイッチになりました。もちろんSETも、SETの芝居も大好きでしたから、退団というよりはのれん分けをさせてほしいと三宅さんにお願いして、自分たちの演劇ユニット 「地球ゴージャス」 を立ち上げたんです。
SETから独立した僕たちは、とにかく今の考えや思想、生き様を見せていくことにこだわりました。その理由は明確。たとえば、僕は大阪出身で、阪神・淡路大震災の際、近くにいながら何もできないという経験をしてきました。そのとき、とてつもない無力感に襲われました。だからこそ、芝居を通じて、世の中に自分たちができることをしたかった。自分たちにできることは何か? それは舞台を作ることしかありません。心に余裕ができはじめた人を、より豊かな気持ちにさせるエンターテインメントを作りたい。どうせならば、日本だけでなく世界の人たちをゴージャスな気持ちにしていこうじゃないか‥‥。そうして生まれたのが、「地球ゴージャス」 なんです。
この演劇ユニットでは、基本的には五朗が作・演出として台本を書くのですが、世相とのバランスを常に考えるようにしているんです。たとえば世間が割と平和なときは、攻めの話を作ってみたり、きわどいところまでテーマを掘り下げる。逆に、今の時期みたいに、東日本大震災の傷が癒えていないような時は、日本全体を楽しく元気にするような話を作るとか。現実がつらいときだからこそ、楽しさが前面に出てくるほうがいい。
だからこそ、今回の新作 『海盗セブン』 では、とにかく清々しいほどにバカバカしい話を作っています。バカバカしいことを、単なる悪ふざけではなく、非常に高い水準のレベルでやっていく。極めた上でのバカバカしさとでも言いますかね。
演劇活動もさることながら、テレビへの露出も際立ち始める。ドラマ 『相棒』 での亀山薫役はもはや説明不要の認知度だが、それ以外にも 『王様のブランチ』、そしてNHKの連続テレビ小説 『おひさま』 など、注目度の高い作品や番組でキーになるポジションを担い続ける寺脇氏。こうした大役をこなしていく中で、俳優としてどのような意識の変化が見られたのだろうか?
『相棒』の亀山薫が教えてくれたこと

これは 『相棒』 で亀山を演じさせていただいてからの変化なのですが、役を作るという意味がまたひとつ開けたと思っています。最初のうちはね、「ここでこう言おう、こういうふうに動こう」 と、役としての動きを頭で考えていたんですよ。でも役を演じるというのは、そういうことではないと気付いた。そこで(現場で) 役として生きていればいいだけなんだ、と。亀山を演じ始めて5~6年たった頃でしょうか、「演技をしに行くのではなく、亀山薫になりにいけばいいんだ」 と気付いてフッと肩の力が抜けましてね。ジャズなどのセッションも似たようなものかもしれませんね。セリフだけ覚えて行って、そこで感じたままにセッションをしていくわけです。
その再発見が、NHKの 『おひさま』 でもできたのだと思います。娘役の井上真央ちゃんや永山絢斗くん、田中圭くんらのしゃべり方を聞いて、自分が感じたままに 「須藤良一」 という役で動いていく。もちろん、脚本家の岡田惠和さんの書くシナリオの妙もあります。僕自身、こんなに泣いた作品もないですからね(笑)。 最初にシナリオを読んだときの感情を大事にし、台本になくても泣けるところだったら泣いてみる。役としての感情を、そのまま素直に出せばいいだけですから。
役者ってね、自分の中にないものは出ない職業だと思うんです。だから 『おひさま』 の須藤良一にしても、そのときどきに、自分がどんな人間であり、何に対してどんな感情を持てる人間なのか、発見する楽しみを今抱きながら仕事ができています。若い頃とは違った成長ができるきっかけを知りましたので、今後の自分の演技がどのように変化していくか、とても楽しみですね。もっとも、感じたことを素直に出す、そのシンプルなことを続けていくだけですけれども。
(インタビュー・文 新田哲嗣 / 写真 Nori)