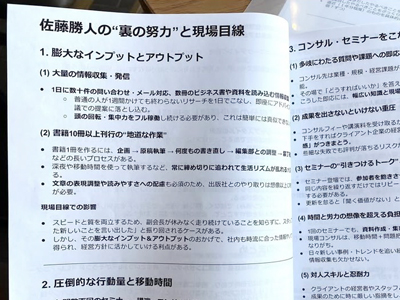道徳心と言われるとフワフワしすぎて何のことかわからなくても、修身と言われれば一定の理解が出てくると思います。この違いは何なのか。言い換えれば、修身の中身は道徳心に他ならないのに今この2つが重ならないのはなぜなのか。誰が・いつ・どんな目的で、道徳心を“それ”と得心できなくさせたのか。この点については本書42、43ページ、48~50ページに端的に書かれています。他にも、元の番組には随所に著者の戦後歴史観が展開されており、書籍で割愛された内容も多いので、そちらも参照されるようお勧めします。
全体的に、「言われてみればそうかも・・・」と感じる箇所が多々ある本でした。例えば以下の一節。
「世界の歴史を見れば、藤原氏のように強大な権力を握った氏族は、リーダーである国王や皇帝に反旗を翻し、自分たちが新権力者になろうとするのが常であった。‥略‥日本ではいかなる状況となっても自ら天皇になろうとする氏族は出てこなかった。これが世界と比べたときの日本史の大きな特徴である。」(p192)
物事の由来とか根っこは為政者(GHQ)の画策で隠蔽ないし歪曲されていても、なくなったわけではありません。である以上、それがこうして新書の一節などにポロッポロッと現れてくるのが歴史の怖いところ。「そう言われてみれば・・・」の感覚を頼りに本書を読めば、天皇と国民の関係性以外にも、日本および日本人の歪曲される前の姿への気付きがたくさん得られそうです。
恥ずかしながら評者も歪曲に乗せられていたことを告白しつつ、例えば教育勅語について。もしかして、教育勅語は軍隊で若い兵卒を教化するためのものだったと、何となくのイメージで誤解している人は多いのではないでしょうか。しかし、本書18ページには、学童教育の科目としての「修身」と教育勅語との関係が以下のように書かれています。
「当時(江戸・明治初期)の知識階級は非常に混乱した。その情勢に危機感を持たれた明治天皇が、古き良き日本を取り戻すために、そして日本の教育のために発布されたものが「教育勅語」であり、それを具体的に解説したものが「修身教科書」であった。」
さらに45ページにはこうあります。
「教育勅語が発せられた明治23年(1890)は、ほとんどの大人が江戸時代に生まれた人たちである。江戸時代、庶民の忠義の直接の対象は天皇ではなく、それぞれの地域の殿様だった。‥略‥西洋列強に対抗するために日本は、西洋流の近代国家の体裁を整える必要があったのだ。」
この時代に東アジアや南アジア諸国が次々と西洋列強の植民地化の餌食にされたのは、それらの諸国が近代国家になれなかった(小国の集まりのままだった)から。日本も藩の集まりのままでは同じ目に遭っていたでしょう。天皇制も、修身も、その中身である教育勅語も、第一義的には自国を西洋列強から守るための――非常に誤解を招きそうな言葉ですが――工夫だったのではないか。だからといって威信が落ちるわけではなく、むしろそれができる唯一の存在が天皇であり、その系譜がせいぜい15世紀の封建領主上がりの西洋の王族と違って控えめに見ても3世紀まで遡れる歴史を持っていたところに、日本の強みがあったわけです。
そうとわかれば、修身も教育勅語も、変なアレルギーなしで受け入れられるはず。そうして素直に本書の内容に入っていけば、修身、の中身だった教育勅語、の基になった「心学」に突き当たります。徳川八代将軍・吉宗の時代に石田梅岩という学者が興したこの学問の教えを、著者は平易な言葉でこう解説してくれます。
「人間はみな心を持っている。道徳心を育むにはその心を磨けばいい。心とは玉みたいなもので、それを磨くには儒学でもいいし、仏教の教えでもいい。あるいは神道、武士道、キリスト教でもいい。日々、正しい行いをしていく中で心を磨けばいい」(p29)
教育勅語は天皇の繫栄を願うものだとか、国家神道の強制や軍国主義を招くものだとかいう、流布されたイメージが解きほぐされる、新鮮な一節。むしろ特定の宗教に頼らなくても平均的な民衆が各々の“お天道様に見られている感覚”でこれができるのが日本民族の美風だったのであり、一時代の歪曲でそれを損ねてはならないことを、本書は訴えかけているようです。
これらの教えをもっともっと長く講じてくれるはずだった渡部昇一氏は、4月17日、86歳で永眠されました。哀悼とともに、拙文を捧げます。