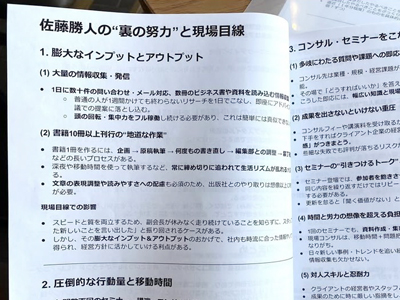有料アプリを買い、金を払ってまで、「お前の顔なんか見たくねーよ、バーカ!」と思われている広告がある。かたや、お金を払いわざわざ注文をしてまで、消費者が喜々として、炭酸水の生産者である企業にとって需要の最前線である冷蔵庫の上に貼り付けられる広告(評者注、Amazon Dash)もある。/この絶望的なまでに埋めがたい差は、何がもたらしているのだろうか。/‥略‥/これからの広告は、欲望を喚起させるのでなく、欲望を充足させるものになるべきだ。そして欲望は、広告が一方的に作り出すのでなく、消費者が主体的に感じるべきものだ。
(「AdverTimes」オーケー、認めよう。広告はもはや「嫌われもの」なのだ 2ページ目より)
Amazon Dashはアマゾンのサービスですが、本書で松島氏が繰り返しフォーカスするIoT――「先端的な研究機関や大手コンピュータメーカー、システム会社が提唱・主導しているのとは別のIoT」(p50)――にも、同様のことができるはずです。IoTの本丸はむしろRaspberry Pi(ラズベリーパイ)などを使って末端の零細業者も同様のことが始められる点にあり、そういったIoTがシェアリングエコノミーと合わさってもたらす世界はユーザーエクスペリエンスの観点からはAmazon Dashの先を行っていることが、例えば本書50ページ以降を読むとよくわかります。
それは一つには、街の業者が何々Dashを展開している点において。そしてもう一つには、その時の「業者」はもはや企業というより個人ユーザーである点において。コンシューマー(消費者)とプロデューサー(生産者)が一緒になったプロシューマー(生産=消費者)という概念も、本書の鍵になります。
「UXの時代は消費者が生産者になったほうが良いものが生まれる」――本書はまさにこの趣旨を地で行っているというのが、評者の理解です。センシング技術とIoT、IPv6とナローバンド、ビッグデータにAIにクラウドサービス、M2MにP2P、等々。各技術トピックが既存の産業にどんな変化をもたらすかがわかりやすく描かれている点は多くの人がAmazonレビューで褒めている通りですが、ライターでもある評者としては、文章がよく練られている点に感心しました。技術的な内容についてはさておき、地の文で、言葉の選択がいちいち繊細なのです。「他のどの語でもなくこれか!」と感じる箇所が多々あったのは編集協力の原修二氏のお手柄でしょう。同氏は著者がUXビジネスの一環で発行人を務めるトライアスロン専門誌でライターをされている人物のようで、評者の思い込みでなければ、お互いが相手のため本当にいい仕事をしようとした雰囲気が感じられます。巻末の松島氏の謝辞の文面にも、その雰囲気が残っています。
そう思って出版元のホームページを読むと、端々に本書の主張と相通じるメッセージがありました。「共有」「想像力」「パブリック(公)」といった語はそのまま本書のキーワードでもあります。会社概要を見ると、著者と同じアンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)出身の役員が多く、出版元としても相当思い入れを持って松島氏の処女作に取り組んだのではないでしょうか。また、カテゴリー「英治出版について」から「採用情報」>「出版プロデューサーの仕事」と遷移したページには、本書奥付に記載されたスタッフが何人か名前付きで登場し、ユーザーエクスペリエンス志向で本づくりを行う同社の様子が生き生きと描かれていました。
これらの要因が働いたからこそ、本書が総じて“気持ちのいい一冊”になったのではないか。上製で紙もいいものを使っているので価格はやや高めですが、プロシューマーの時代を迎えた今、背景も含めて、学ぶべきヒントが多いと感じた一冊でした。お勧めです。