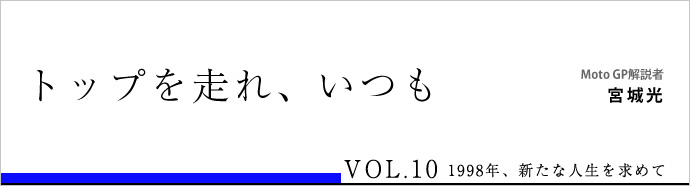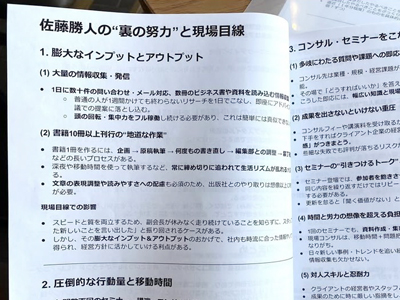Vol.10 1998年、新たな人生を求めて
日本国内の最終履歴は「大きな事故を起こして走る場所が無くなった元ライダー」であり、「30歳を超えた出戻り」という訳だ。日本に私の居場所などあるはずがない──そう思っていたから、ずっと私を気にかけてくれていた当時の本田技術研究所副社長である篠崎隆さん、ホンダのモータースポーツ本部長、菅原冠さんらホンダの関係者に報告をするための帰国も、「ちょっと日本に旅をしてくる」くらいのつもりだった。
ニューポートビーチの自宅はひとまず家財道具一式とともに知人に貸し出し、「帰国」したのち、これからの生き方を焦らずにじっくり考えよう──そう思っていたのだ。
だが、菅原さんは私にこう言う。「宮城君には、日本でやってもらいたいことがたくさんある」。
掘り起こされた「商品価値」
自分で気付かない「商品価値」を外から見い出されることがあるのもまた、ビジネスのおもしろさのひとつかもしれない。ホンダからのオファーは、自分でも考えつかないようなものばかりだった。
ひとつは、ホンダがモータースポーツと同じくらい力を入れていると言っても過言ではない「安全運転活動」の講師としての仕事だ。なるほど、「誰が最も早く規定の距離を走りきるか」を競うのがモータースポーツの原点である以上、レーシングライダーは、ただの「命知らず」では務まらない。レースで経験してきたことは一般のライダーにもフィードバックできると思ったが、ホンダが注目したのは、私が交通事故で選手生命を断たれかけた経験──私が1993年に渡米するきっかけになった事故だ──を持っているということだ。
高い技術を持ち合わせていても、事故には遭遇しうる。ならば、一般のライダーはどのように走るべきなのか? 頭ごなしに「啓蒙」するのではなく、バイクを愛する一般のライダーの心理も理解したうえで同じ目線に立って講話や講習会を実施することで、多くのライダーが「聞く耳」を持ってくれるようになった。
そしてもうひとつは、当時ホンダが創業50周年に向けてレストアに勤しんでいたヒストリックマシンのテストライダーとしての仕事だ。
メカニズムを熟知したうえで走らせることができ、しかもレーススケジュールに左右されない、引退済みのライダー・・・。その条件にも、私はぴったりと合致したのだ。
ホンダが世界に打って出た1960年代のレーシングバイクは、現代ほど技術が発達していない時代のプロダクトであるがゆえに、エンジンに繊細な扱いが求められる。常に「エンジンの中がどんな状態なのか」を感じ取りながら走る必要があり、少しでも雑に扱えばトラブルの元にもなりうる。当然のことながら「代わりのマシン」など存在するはずもないから、絶対に転倒はできない。
「エンジントラブルを原因とする転倒」が、レースキャリアを通じてほとんど無い(エンジン以外のアクシデントによる転倒は数え切れないほど経験したが・・・)私は、まさに適任と判断され、現在にいたるまで続く「動態確認テスト」の仕事の第一歩となった。
*
「2輪レース人生」を終えた自分は、何をしたいのか? おぼろげだったその答えは、ホンダとの新たな関係の中で徐々に明らかになっていく。それは、まるで子どものようにシンプルなものだった。
自分が一番成し遂げたいのは、「バイクに乗り続けること」。レーシングライダーとして「トップを走ること」も、その一部だったのだ。
世間の捉え方とは違ったホンダからの提案に、自分では思ってもいなかった時間がスタートした。
──第11回に続く
(構成:編集部)
「トップを走れ、いつも」
vol.10 1998年、新たな人生を求めて
(2015.3.18)