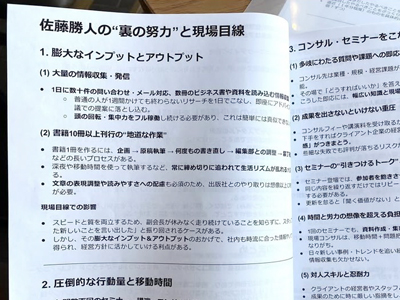vol.2 1993年8月 静寂のデイトナ
運命のタイムアタック
アタックを開始する。
レブカウンターは11,000rpm、290km/hをマーク。しらけた顔でコース脇に立つダンも、ストップウォッチをセットしたはずだ。そこから左に大きく回り込みながら、インフィールドセクションに突入する。「ホースシュー」と呼ばれる、馬の蹄のようなコーナーは、2速。そこから一気に加速し高速の左コーナーが「キンク」だ。ここは4速で、いかにスロットルを戻さずにスピードを乗せられるかがポイントだ。フレームがよじれ、サスペンションは暴れ、頼みの綱のブリヂストンタイヤが接地感を失いかける。最高速をマークするオーバルセクションとは異なる恐怖が全身を襲う。
ヘアピンをクリアすると、インフィールドセクションの出口が迫る。リアタイヤが滑り、フロントが浮き上がろうとする挙動と格闘しながら、「絶対に戻すものか」と、コーナーの出口をにらみ続け、一気に30度バンクの最上段まで駆け上る。
──そういえば、両足にはまだステンレスのシャフトが二本埋め込まれていた。絶対に転倒はできない。限界を超えるのではなく、内側から少しずつ叩き出すようにして、限界点を拡張していく。
最高速を稼ぐために、「すり鉢」の上側を走り、バックストレッチでは300km/hに到達する。シケインに向けて180km/hまで一気に減速、ここをクリアしたらふたたび全開。この「じゃじゃ馬」に鞭を入れ、30度バンクの上段から下段へと駆け下りながらメインストレッチへと戻るのは、私にとっても「恐怖」でしかない。それでも、ノーマルの124馬力から約50馬力も上乗せされた、直列4気筒エンジンをレブリミットで絶叫させ続ける。──ふたたびコントロールラインを通過。
遮二無二走った、とはこのことだろう。多くのレースを戦ってきたが、あれほどまでに「心臓が喉から飛び出しそうだ」と感じたことは無いような気がしている。
あのNSRに比べれば・・・
テストを終えて、ベストラップは1分56秒後半。チームのレギュラーライダーのトミー・リンチらのタイムを約1秒上回り、非公式とは言え、このサーキット、このクラスにおけるコースレコードを記録していた。
レギュラーライダーも黙ってはいない。すぐさまコースインしてアタックをするが、最後まで私のタイムに届くことはなかった。つい数時間前とは打って変わって、メカニックのダン・カイルが、チームオーナーのケビン・エリオンとともに、ほくほく顔で近づいてくるのを見て、苦笑を禁じ得なかったものだ。
・・・なぜそんなことができたのか。当時は見つめ直す余裕すら無かったが、おそらく「恐怖」の限界点が高いところにあったからなのだろう。
日本国内でレースをしていたホンダワークスのNSR500は、115kgという軽量な車体に180馬力を発生させる2ストロークエンジンを搭載した、「じゃじゃ馬」どころではない「モンスターマシン」だった。
何もかも失っていたような気がしていたが、「あのNSRに比べれば・・・」という、ほんのわずかな余裕が、限界に挑むための力になっていたのだとすれば、私にチャンスを与えてくれたのもまた、過去に積み上げてきた能力と経験だったのではないだろうか。
そのテストの写真は一枚も無く、この出来事を知るのも、限られた人々だけだ。物語のように話したら、あまりにできすぎの自慢話のように聞こえてしまうかもしれない。
それでも、当時はただがむしゃらに挑むしかなかった、数々の「点」を「線」として紡ぎ、意味を見いだせるようになった今だからこそ、思うことがある。
それは、この「運命のデイトナ」で「期待以上のもの」を相手に提供するというビジネスを成功させたことが、その後の私のキャリアをかたちづくり、今に繋がっているのは、紛れもない事実だということである。
――第3回に続く
(構成:編集部)
「トップを走れ、いつも」
vol.2 1993年8月 静寂のデイトナ