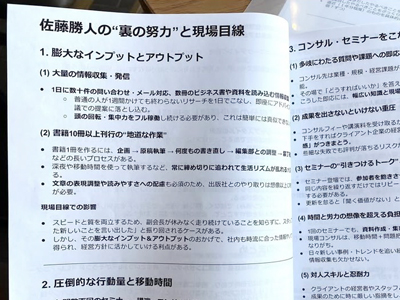トピックスTOPICS
かつて“天才”と呼ばれた日本人ライダー・宮城光氏が語るオートバイレースの世界。第2回からはノンフィクション・ルポルタージュの形式で、本人の体験を臨場感たっぷりにお送りします。時は今をさかのぼること21年前、1993年8月のアメリカ・フロリダ州デイトナから――。
言葉はわからなくても、「誰なんだよ、この日本人は」と、顔に書いてあるのはわかった。なぜ、よりにもよって、10位がいいところの後方でうろちょろしているだけの、無名の東洋人がテストライダー? 私が、目の前にいる堂々たる体躯のアメリカ人メカニック、ダン・カイルの立場でもそう思っただろう。
「お前、本当に乗れるのか?」
ホンダ・CBR900RRにまたがった私に、ダンが念を押すように声をかけてきたのを覚えている。ヘルメットの中から「イエス、イエス」と受け流すように応えたことも、不気味なまでに静まりかえって、青い空の下にそびえ立つ巨大なグランドスタンドの光景も・・・。
1993年。交通事故による両足骨折からホンダのワークスライダー(メーカー直系チームのライダー)の契約を失い、バブル経済の崩壊により、活動を縮小させていた国内のレーシングチームとの契約にも至らなかった私は、アメリカにいた。
──テキサスはダラスから車で30分、キャロルトンにあった、モトリバティという小さなチームに所属していた当時の写真は、手元には無い。小さなレーシングチームでグリッド後方から出走する、どこの馬の骨かもわからないライダーを好きこのんで撮影してくれるカメラマンなど、どこの国にも居はしないからだ。アメリカのレーシングチームも、レースファンも、メディアも、誰も私のことなど見ていないし、認識さえしてくれていなかっただろう。
トップを走らなければ注目もされず、したがってチャンスも得られないのが、プロのモータースポーツの世界。20歳でレースデビューをして以来、常に恵まれた環境で(それを自らの力でつかみ取ってきたという自負はあったが)国内レース界の日の当たる場所を歩いてきた私にとって、屈辱的だったのは確かだ。
私は30歳にして、「ワークスライダー」といった肩書きも、「有力チームのシートを若くして得た天才」という過去も持たない、一人のライダーになっていた。
その年の2月、AMA Pro Racing――アメリカン・モーターサイクリスト・アソシエーション(全米モーターサイクリスト協会)が主催する米国内ロードレースの最高峰。通称「全米選手権」――の開幕戦、フェニックスでのレースは、なんとか完走。日本国内と違うレギュレーションや環境の違いに驚くばかり。第2戦、3月のデイトナでのレースは、後方から追突される憂き目に遭い、右ひざの骨折・リタイア。ダメージのリハビリとトレーニング、鈴鹿8時間耐久ロードレース(通称・「8耐」)参戦のための一時帰国を経て8月、シアーズポイントの復帰戦で16位。続くミッドオハイオでは10位。数字としては上向きではあるが、誰にも注目されないという状況は変わらなかった(唯一の例外は、「お前、最近なかなかイイじゃないか」と声をかけてきた米国トップライダーの一人、ジェイソン・プリッドモアだが、きっとそれも気まぐれみたいなものだろう)。
それだけに、突如舞い込んできたオファーは信じられないようなものだった。
・・・日本のタイヤメーカーであるブリヂストンが、デイトナ・インターナショナル・スピードウェイで性能テストを行うにあたり、テストライダーとして私を指名しているというのだ。
レーシングタイヤは、言うまでもなく「タイムを削る」という機能製品。ゴムの組成の化学式を「ラップタイム」として数値化し、価値を見いだすための場が性能テストだ。誰にでもできるものではなく、速いライダーにしか務まらない。
「敗者」である自分を、わざわざ指名することの理由として、「日本人スタッフと日本語で会話ができる」という以外に思い当たる節があるとすれば、8耐に出場した際、優勝した「ミスター・デイトナ」ことスコット・ラッセル──このライダーは、他社のタイヤを装着していた──とほぼ同等のラップタイムを決勝中に記録できていたことだ。
私を指名してくれたのは、ブリヂストンの日本人エンジニアである藪田さんだという。8耐でレースを走りきってのリザルトとして見るべきものがほとんど無かったにも関わらず、この、ほんの小さな事象を以て、私という存在に意味を見いだしてくれる人がいたのだ。私は、たちどころに世界とのつながりを取り戻したかのような気分になり「藪田さんのために、全てを出し切ろう」と考えていた。
クルマでまる2日をかけ、疲労困憊で約5ヶ月ぶりに訪れたデイトナ・インターナショナル・スピードウェイは、春に訪れたときとは異なり、静まりかえっていた。
秋から冬、そして春に行われるビッグレースが夏場に開催されないのには、理由がある。暑さと日差しがあまりにも強烈で、参加する選手もマシンもピットクルーも、そして何よりレースファンも音を上げてしまうからだ。春に訪れた時には多くのレースファンで埋め尽くされていたグランドスタンドも、今回はまったく人気が無い。テストを行うにはもってこいというわけだ。
コースは競輪のトラックのようなすり鉢状をした「オーバルセクション」──これは、平均時速300kmにも達するとてつもないスピードで周回を続けるという、なんとも豪快な内容からアメリカで絶大な人気を誇る「NASCAR」のレースの舞台となる──と、いくつかのカーブを組み合わせた「インフィールドセクション」から成る。
まさに「アメリカらしさ」「アメリカのモータースポーツ文化」をも語るようなデザインのコースでタイムを削るための「秘訣」があるとしたら、それはただひとつ。恐怖に打ち勝ち、「全開」でいられる時間をいかに増やすか、だ。
それこそ「どこからかふらりとやって来た東洋人のライダー」が本当に、このコースで性能を評価できるのか、チームの人間が疑問に思うのも間違いないのだ。
私が参戦していた全米選手権の600ccクラスよりも上位のカテゴリーのマシンであり、しかも、トップチームのひとつであるツーブラザーズ・レーシングのチューンしたCBR900RRは175馬力を超える、ハイレベルなバイクだった。だが、コースインしてわかったことがあった。とにかくパワーだけが突出していて、コーナリングでは盛大な振動と共に車体が暴れまわる・・・正直に言えば、日本で乗ってきた同クラスのマシンよりは、1周あたり1秒以上は遅いレベルで成立しているモノだったことだ。
ライダーの勇気を試すかのようなこのバイクに乗って、これから、勇気を試すかのようなコースに挑む。誰からも認識されなくなっていた自分が、ふたたび存在する意味を取り戻すには、ここで結果を見せるしかないのだ。「チャンスを掴もう」といったギラギラした気持ちを抱く余裕は無かったが、フロリダの空の色もあってか、悲壮感も無かった。
-
前の記事

トップを走れ、いつも vol.1 レースはドラマ トップを走れ、いつも
-
次の記事

トップを走れ、いつも vol.3 「76番手」から栄光を目指して トップを走れ、いつも