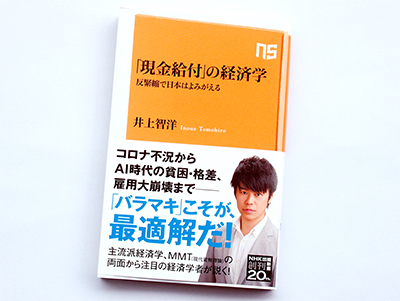著者は朝日新聞経済記者の福田直之氏。本書は2017年4月から昨年8月まで著者が北京特派員として中国経済を取材した記事に大幅加筆と最新情報を受けた差し替えを加えて完成したそう。今年3月1日公表のアメリカ国家安全保障局(NSA)の報告書も踏まえているようなので、紙の書籍としては獲れたてぴちぴちの情報でできているのではないでしょうか。
読んでいくなかで最初の驚きは「はじめに」の35行目にありました。「本書の内容は以上のようなものだ」とあり、「え?」と思って遡ると、15行目~34行目が丸々本書の概略になっていたからです。
概略の概略ですし、ここだけ読んで一冊読んだつもりになるのはネット記事でありがちな「見出しだけ読んで全部読んだつもりになる」勘違いと同じですが、もったいの付けなさ加減が思い切っているというか、それだけ著者も内容に自信があるのではないでしょうか。事実、書籍としておもしろい、どんどんページをめくらせる本になっていることは、漫画にたとえて説明した通りです。
全体は5章構成ですが、読めばすぐ、抽象度の階層を一つ上に上げるとⅠ、Ⅱ、Ⅲの3部構成になっていることがわかります。すなわち、
第1章 AI大国が突っ走る
第2章 監視社会
第3章 中国技術のアキレス腱
の第Ⅰ部、
第4章 社会主義下のイノベーション
の第Ⅱ部、
第5章 ニューエコノミーの旗手たち
の第Ⅲ部です。
第1章から3章まではあれよあれよと読んでいくのでいいと思います。没入して一気に読めます。第5章は人物評伝です。伝記物を読む感覚でワクワクしながら読みつつ、ふと冷めて、「この人こんなに優秀なのに、取り組んだ対象のせいで、他の人と比べると社会的成功の面では損してるなぁ」などと勝手な感想を抱くのも余興のうち。
問題は第4章です。この章だけは、多少の予備的な知見が読む側に求められると思います。読みながら没入を離れて「うーん」と時々考えさせられるのもこの章です。
と言っても、著者の考察に「うーん」となるのではなく、西側の自由主義経済と共産主義の計画経済のどちらが社会厚生に資するか――少なくとも一般大衆の生活において――がわからなくなるからです。わからなくさせる程度には共産主義経済思想の妥当性を感じさせますし、自由主義経済の正当性も一般に思われるほど自明ではないことを再認識させられます。「うーん」となるというのはそういう意味です。
評者はここで吉本隆明の「アジア的」という概念を思い出しました。これについては「ほぼ日刊イトイ新聞」運営のサイトから講演音声を視聴できます。小欄vol.64では評の対象書籍のほうから引用しましたが、今回は講演のほうから引用。
「アジア的地域では、極端にいいますと、村落共同体が世界の広さであり、地球が世界の広さではないのです。自分の利害の関係のないところでどんなことが行われようと、自分のところに響いてこなければ関係ないよという考え方は、みなさんのなかにもあるでしょう。アジア人はぜんぶ思い当たるはずです。‥略‥それは〈アジア的〉心性かもしれないと疑ったほうがいいと思います。」(「吉本隆明の183講演」A051「〈アジア的〉ということ」リンク先テキストより)
ニュアンスが落ちている箇所を補足すると、「それは〈アジア的〉心性かもしれない」は、「それは〈アジア的〉心性に過ぎないかもしれない」という意味です。(音声はチャプター「揺れるマルクス」の2:22~3:20が該当。)
本書によれば中国ではAIの社会利用とその前提になる監視社会化が西側諸国より格段に進んでおり、市民もおおむねそれを受け入れているそうで、80ページには精華大学の街づくり関連の教授の言葉で、「衣食住を満足させてくれさえすれば、庶民は政府を支持してきた。政府の対応が権利侵害にあたるかを考える西側とは違う」ともあります。中国新型都市化研究院執行副院長という教授の肩書は勘案すべきとしても、vol.64ラストで引用した通り、日本には「抽象的違憲訴訟」の制度がないのを見ると、案外日本も同じではないか。論理的想像力で身の回りの世界をとらえそれをもとに自身の信条を固める感覚は、中国に限らずアジア人はそもそもないのではないか。そんなふうに思えてきます。(そしてそれは吉本によれば克服できるかもしれない。)
本書が突きつけるもう一つの本質的なテーマに、「戦争に負けるとはどういうことか」があります。
第3章「中国技術のアキレス腱」の第10節「日米半導体摩擦」は、現在アメリカが中国に対しとっている締め付け策が80年代の日米半導体摩擦のそれと同工異曲であることを思わせます。――が、決定的に違うのは、軍事同盟を質にとられる日本がお尻をまくったのに比べ、中国は正面から喧嘩を買って出ているところです。
我々は普段意識していませんが、中国は第二次大戦における連合国側で(日本は枢軸国側)、戦勝国です。米中の覇権争いはどこまで行っても戦勝国同士の争いで、どちらが勝つにしても日本は、歴史を省みる限り目を付けられない程度――「6割」という具体的な数字も146ページに出ています――でやっていくしか許されなさそう。この点も、第4章の経済思想の対立に関してと同じく「うーん」となってしまうところです。
うがった見方をする人、そして陰謀論に立つ人は、「やっぱり朝日だ。こうやって日本人の精神の牙を抜く作戦なのだ」と解釈するかもしれません。そして「経済思想の対立などない。覇権争いも演出だ。すべてはディープステートの采配だ」と理解するでしょう。
しかし、それではあまりに本書が損をし過ぎです。評者としては、「はじめに」の末尾で著者が謙虚に語る通り、「中国の技術や経済を巡っては近年、優れた書籍がたくさん刊行されている。そうした本とともに、読者の皆さんが中国を知るための一助となれば」という位置づけで本書を迎えたいと思います。社会の在り方を考えるうえでも経済の在り方を考えるうえでも、最新の中国をまとめて知ることができる本書は一読の価値ありです。
ここで言う「社会」とは自分たちの現実の社会であることを――吉本の指摘を踏まえて――注意喚起しつつ、『中国の行動原理』*1と『AIと憲法』*2の2冊を副読本に推薦して評を終わります。
*1 『中国の行動原理 国内潮流が決める国際関係』(益尾知佐子著・2019年・中公新書)
*2 『AIと憲法』(山本龍彦編著・2018年・日本経済新聞出版社)