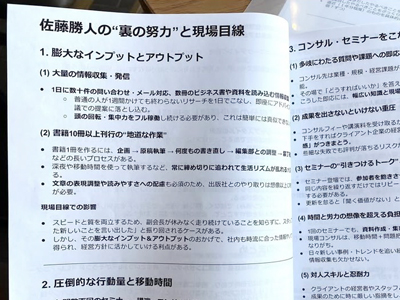その私怨(?)があったからか、今年初回の本欄で取り上げるビジネス書はこの本になりました。帯の表にふわっとした言葉が並び、いかにも大手コンサル会社系の著者が言いそうな中身を予想させます。そう思って裏の帯を見ると、「あー、要は効率化して労働強度を上げて外注で人を減らしてコストを下げましょうってことね。ハイハイ、コンサル屋さんはそうよね」と偏見で思い込みかねない項目が並んでいます。評者がまんまとそう思い込んでしまったのは、そして「チキショー、今月はこれにしてやる!」と購入に及んだのは、店頭で本書を見つけたその日その瞬間、世の勤め人に対するすべての個人事業者の怨念を、一身で代表する思いであったことを、告白しておきます(ゴリゴリの労働強度強化論が展開されるのを期待していた)。
結果、中身は全然違いました。著者と担当編集者にお詫びします。まず「外注して人を減らして」について、そうではないことがわかる箇所を列挙します。
「本来、スキルとは、様々な業務や場面で活用できるものなのです。/にもかかわらず、なぜ「業務経験=スキル」になったかと言えば、‥略‥定められた業務を行なうことが個人の価値であり、個人に求めるものと考えていたのです。」
「(本来やる必要のない業務を仕方なく続けていたりする)一方で、新しい機能・業務を強化する際には、社内に人材が余っているにもかかわらず、その業務経験のある人材を、わざわざ外部から採用しているのです。/こうした考えやマインドこそが日本企業の生産性(労働生産性)を先進国最低水準に引き下げてしまった要因です。」
「個人のモチベーションや、いまあるスキル・強みを活かすことで、個人のパフォーマンスは短期間で大きく高めることができるというのが、私が長年実施してきた人材変革の支援から得られた結論です。」
「(足りないケイパビリティ・機能を人材スキルのレベルまで落とし込んで)マッチングを進めていくと、機能を強化するために、どうしても足りないスキルはそれほど多くはないことがわかるはずです。」(第3章 人材の提供価値を変える p157、158、165、174)
最後の引用の隣のページには、「それでも社内で調達できないスキルがある場合は、外部から採用すればよいでしょう」という記述もあります。正規雇用を減らして労務費(=人件費)を減らしてコストを下げて、という話ではないことがよくわかります。
また、評者の思い込みのもう一つの要点、「コストを下げましょう」をめぐっても、単に原価を項目ごとカットして支出を減らそうという話ではないことが、第2章「コスト構造を変える」で詳述されています。一例が以下。
「資産は、支払いの額をベースに取得金額が計上され、保有している間は取得金額をもとに会計処理されます。つまり、企業におけるコスト構造は、すべて支出・支払いベースでとらえられており、肝心な価値ベースでは把握できていないのです。/しかし、「支出・支払い」とは、企業活動の手段であり目的ではありません。」(p78)
会計的なとらえ方のせいで企業の事業活動が掣肘される様は、財務省が財政規律をタテにやるべきことを行政府にさせないようなことです。「経理部は社長より上か下か」というのは企業でも永遠のテーマですが、とにかくも、見ている世界が違えばそもそも共通言語が成り立たないのだということは、経営者のほうでわかっておく必要があるのでしょう。
そのうえで、著者はコスト構造について、[固定的←→変動的]軸と[転用がきかない←→転用がきく]軸からなる四象限マップをもとに、4つのシナリオで変革することを提唱します。その4つとは、
1、転用できない固定費を減らす
2、減らせない固定費はより価値の高いところで使う
3、固定費を変動費化する
4、コストの転用化を進める
です。
それぞれ詳細は本書に当たっていただくとして、具体的な事柄をエッセンスで示せば、順に、
a、コストレートからではなくチャージレート――時間あたりに顧客に対し請求する金額(売価)――から見るべし
b、固定コストは徹底して新サービスや新事業に振り向ける
c、シェアード部門の“脱下請け”=プロ集団化
d、人材を含む社内リソースを異業種とシェアする
となります。
ただ、現実には、もしかしたら著者の趣旨とは違うかもしれない方向で、例えば3つめ(3-c)に関してはいわゆるクラーク職は急速に派遣業者とAIとRPAに取って代わられつつあります。「シェアード部門のプロ集団」と聞いて「パソナ?」と思う読者は多いはず。
また、4つめ(4-d)に関しても、自動車産業がEVの台頭で擦り合わせ型(インテグラル型)から組み合わせ型(モジュール型)へと産業形態が移行している現状や、あるいは、OEM生産が広まるにつれどのジャンルでも尖った個性の商品が現れにくくなる趨勢を思えば、「メリットはあるだろうけど、なんだかなぁ」という気持ちが、なくはありません。
いっぽうで、各種報道を見る限り、確かに上記4シナリオをやっていそうな企業ほど業績が良いらしいことは事実です。そして、やや総括的なことを言えば、本書の説得力の確かさも、こういうところにあるような気がします。
とはつまり、書かれる内容が、戦略論的な理論先行モデルではなく、事実の追認モデル――ただし良質な――で成り立っているのです。
この特徴は全体の終盤、第5章232ページの記述が、いみじくもその解説になっています。著者によれば、現在、コンサルティングファームがクライアントから求められるものが「戦略策定の支援」から「効果創出の支援」へ変わっているとのこと。水先案内人ではなくパートナーになることを求められる。戦略(=頭脳)よりもオペレーション(=体)にコミットするよう求められる。なるほど道理で、戦略論にふけっている暇はなさそうです。
そう思って本を閉じ、表のタイトルをふと見返すと、『オペレーション トランスフォーメーション』。タイトルに嘘がない本だったことを再確認しました。年頭に際し、経営者は一読の価値ありです。お勧めします。