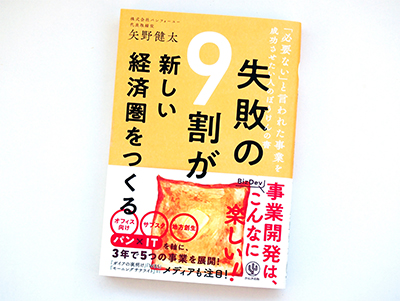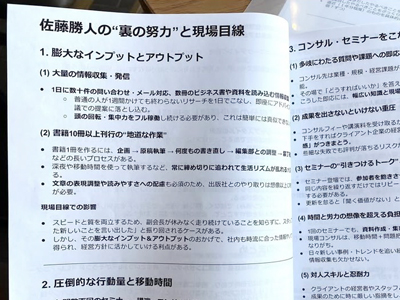2人は基本スタンスが違っていて、彼は「人間は空を飛んでいた頃の記憶というか素養というか、そういうものを意識のどこかにまだ持っていて、それが発動して飛べるのだ」という派。対して評者は、「人が空を飛ぶときは“空を飛ぶ人”なるものがどこか遠い高いところから自分に降りてきて、それで飛ぶのだ」という派。
もちろん2人とも科学的根拠などなく、中沢新一の『チベットのモーツァルト』を引き合いに「人が壁を抜けるとはどういうことか」といった話を援用するぐらいでしたが、そんな論拠から延々自説を発展させて一緒に検討して結局どちらが正しいとなるわけでもない議論に時を忘れることができたのは、若さだったでしょう。
本書は「運動した時に脳がいかに働き、技を習得する過程で脳がどのように変化するかを知ることで、スポーツに打ち込む人々は新たな視座を獲得し、観戦者たちも新鮮な感動を覚えることが出来るのではないだろうか」(p20)という趣旨で書かれた一冊。中を読むと、アスリートたちのパフォーマンスはいかに人智を超えたプレーに見えても、反復練習で脳に刻んだプログラムが発動した結果以外の何物でもないことが、神経科学(脳科学)の知見から解説されます。「人が空を飛ぶときにはどうなって飛べるのか」は、友人のほうが正しかったわけです。
ただ、反復練習といっても普通の練習をしていては「飛べない」よう。第2章「脳に生まれるプログラム」ページ88では、フロリダ州立大学の心理学者アンダース・エリクソンによる実験とともに、「デリバレートプラクティス(計画的な訓練)」の定義が示されます。
・明確な目標を掲げ、そこに到達すべく精密に構成された練習であること
・弱点を克服するために、具体的な課題が課されていること
・上達に向け、ちゃんと正しい方向に向かっているかどうか、第三者(コーチや先生)によって注意深くチェックされていること
そのうえでエリクソンは、上達のためにはデリバレートプラクティスと、対価が得られる「Work」、やること自体が楽しい「Play」という3つの要素が必要だと説きます。それらがそろっている環境が、例えばテニスなら、アメリカにあるIMGアカデミー。錦織圭選手が13歳から留学したテニスの英才教育の学校です。同校出身でかつて活躍した元選手にはアンドレ・アガシやピート・サンプラスらがいて、女子で現役のマリア・シャラポワ選手もここで育っています。
第2章のこのあたりからテニスの話が増えるのは、本書が神経科学者の小林耕太氏とテニスライターの内田暁氏との共著だから。内田氏がテニスの世界ツアーを回って取材したトップ選手たちのエピソードが随所に挿入され、その背景を神経科学的に推測・解説する内容を基本の一つとして本書は進みます。
例えば2016年の全米オープン女子3回戦。当時18歳の大坂なおみ選手が大番狂わせまであと1ゲームに迫りながら突如として乱れ、そのまま逆転負けを喫した例は「チョーキング」として解説されます。チョーキングは別名「スポーツ不安」とも呼ばれ、極度のプレッシャーや緊張状態に耐えきれずにパフォーマンスが劇的に下がり、思考も混濁してしまうこと。似た症状で「パニキング」もあり、いずれも脳内のプログラムの不調、あるいは不足によって引き起こされるそうです。
皆さんも、例えばプレゼンの席などで急に頭が真っ白になり、何をどう言えばいいのか、なぜ自分がここにいるのか、わからなくなった経験がありませんか? そういった経験がトラウマになって苦手意識を持ってしまっているビジネスの場面が、1つ2つ、あるのではありませんか? 神経科学的にその原因がわかれば対策も打てようというもの。テニス好きかどうかに関係なくビジネスパーソン向けの媒体で本書を紹介する理由はまさにそこです。
他にも、「チャンキング(複数の事象をひと括りの塊で記憶すること)」の崩壊でノバク・ジョコビッチ選手に敗れたというロジャー・フェデラー選手のエピソード(p196~200)からは、同様に勝負とは別に対話の美しさが問われる競技の代表はやはり将棋だろうか、とか、リング上で敵と1つの物語をつむいでいく競技とされるプロレスはつまりテニスの何十倍かの緩慢さでチャンキングを繰り広げているのだろうか、とか、そんな連想も楽しめました。
スポーツにからめた雑学本として読むもよし。トップアスリートの脳で起きていることに学んでビジネスのパフォーマンスを上げるもよし。目的に合わせて読める一冊です。
個人的には、アナ・クルニコワの出現を機にロシア人選手が急にランキングトップ勢を占めるようになった話(p107~109)からは、「飛ぶときは“空を飛ぶ人”なるものが降りてくる説」の匂いを感じました。しつこい? 本気です。