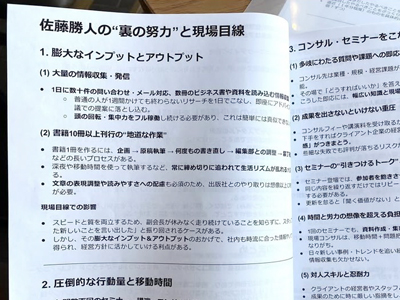Vol.11 もっと「バイク」を伝えるため
「鈴鹿8耐」のピットレーンで・・・
サーキットは自分で「走る」ための場所という、長年にわたって染みついた思考の様式は簡単には覆らない。一年で最も暑い7月末、三重県は伊勢湾にほど近い鈴鹿市の、鈴鹿サーキットに、私はいた。気温30℃を超える炎天下、自分と「同期」のライダーも、さらにはもっと年長のライダーも「少しでも上を」と懸命に走っている姿を見れば「なぜ自分がここで走っていないのだろう?」という気持ちも芽生えるし、ライダーやチームスタッフから向けられる、「レースをやっていた人間が、どうしてこのタイミングで平然とマイクを向けられる?」といった無言の抗議にも心がかき乱される。
醜い、と思われるかもしれないが、自分より一回りも年下のライダーに対してインタビューをする時に、私の中にある「プライド」がちょっとばかりの邪魔をしてきたことも否定しない。
ヘッドセットを身につけ、マイクを片手にピットレーンを歩く私の中には、まさに「複雑」としか言いようのない感情が渦巻いていていたが、私は敢えてそれを胸の奥にしまい込み、疲労困憊で汗みずく、口の端からは涎を垂らし、今にも倒れ込みそうなライダーに向かってマイクを向けなくてはならなかった。
「いま5番手から2番手まで上がってきましたね! どうでしたか!」
自分がバイクを好きになった過程を思い出しながら、人がレースに何を求めているのかを探り、提供の方法を探る・・・その役割を担うことこそが、「走る側」でなくなった自分からレース界にできる恩返しなのだと信じていたからだ。
勝利の瞬間の歓喜の表情を伝えるのと同じくらい、そこに至るまでの苦闘を伝えるのが重要。仮面ライダーがそうであったように、戦いの過程を描いて初めて、人はヒーローに憧れることができるのだ。
レースの「課題」を共有する
私の試みは、当初パドックにおいて評判が良かったとは言えなかった。
自分の経験からも、世界で一番タフな耐久ロードレースである「8耐」で走行直後に的確なコメントを発する自信は無いし、レース中何の遠慮も無く「神聖なる」ピットへと踏み込んでくるレポーターが邪魔でしかないのも理解できる。
しかし、「キツかったですけど頑張りました」の一言をテレビカメラに向かって発するだけで、レースというものの過酷さ、それに挑むライダーの強さ・・・あらゆるものがお茶の間に対して発信され、レースを観る人の胸を打ち、引いては、「バイク」というものの魅力が、まだそれを知らない人に伝わるはずなのだ。
『仮面ライダー555』『仮面ライダー剣』『仮面ライダー響鬼』『仮面ライダーカブト』『仮面ライダー電王』と5年間にわたって8耐に出場した「仮面ライダーチーム」の監督として(35年の時を経て、仮面ライダーの「関係者」になれたのは、ビジネスのことを抜きにして、ただ感慨深くもあった)、あるいは、NHKで放映されていた世界グランプリの実況解説として・・・この頃挑んだ「伝える側」に立っての活動がどれほど効果を上げたのか、正確な数字を把握はできていないし、その全てが「レースを観る側」に受け入れられたとも考えてはいない。
しかし、私の抱いていた危機感は私だけのものではなくなり、ここ日本でレースにまつわるビジネスを行う人々が全員で取り組むべき課題であるという共通認識にはなったと思う。
チームやメーカーとも問題意識を共有し、どのように解決をしていくべきなのかを共に考える中で次第に理解も得られていったし、そのプロセスは私にとって、とても実りのある仕事だった。
*
「自分の好きなこと」を生業にするのは、「『好きなこと』をいかに素早く『現金化』するか」、ということばかりに意識が行き、やがてモチベーションを失ってしまうという危険もはらむものだ。
そんな中、「自分が好きなものを通じてコミュニケーションを取りたい」という気持ちを原動力にしたことで、バイクに関するあらゆる活動に視野を向けられたことは、私にとって幸運なことだったと言える。
スケジュールが過密で体力的にきつくても、あるいは下世話な話、「利益率」が低くても・・・バイクを楽しむ人の前に出て行くのはそれだけで心が通じ合うようで楽しかったし、開発に情熱を傾けるエンジニアたちの言葉を聞けば「早くそれを人に伝えたい」という気持ちで胸が熱くなった。まさに「天職」に出会えたのだと思う。
今、現在進行中の私の生き方の多くは、「どうすれば私の一番好きなものを、もっと多くの人と共有できるか」ということを考え、そして実行した、この頃の体験に支えられている。
──第12回に続く
(構成:編集部)
「トップを走れ、いつも」
vol.11 もっと「バイク」を伝えるため
(2015.4.15)