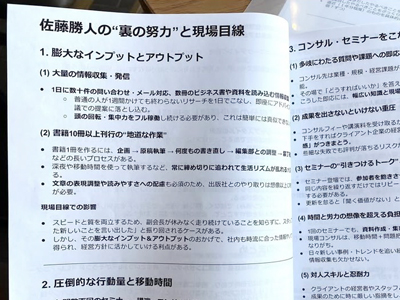トピックスTOPICS
かつて“天才”と呼ばれた日本人ライダー・宮城光氏が語るオートバイレースの世界。「2輪レース人生」を終えてこれからの生き方を模索する中、「バイクに乗り続けること」をモチベーションとして新しい人生の生き方を見いだした同氏は、「伝える」側に立った活動をスタートさせる──。
「2輪レース人生」に終止符を打つことを決めた1998年、世界グランプリのGP500クラスに参戦していたドイツのバイクメーカー、MZのライダーとしてのオファーがあった際には、「やりきった」と決めたはずの心も揺らぎかけた。ホンダが私に多くの(交通事故も含めて、だ)経験を活かした仕事をオファーしてくれたのと同様、「ホンダのNSR500に乗っていた」という経験をはじめとしたレース活動での実績を買ってくれたものだったから、同じように光栄に感じたものだ。
ただ、この年の開幕戦、世界グランプリ・日本GPにスポット参戦した芳賀紀行選手が、ホンダワークスの岡田忠之選手との2番手争いを演じている姿をテレビで見て、「これはもはや敵わない」と感じたのも事実。レーシングライダーは誰だって「自分が1番速い」と信じているし、そうでなければ務まらないが、現役を退いてからもそれを主張するつもりはなかった。
そんな私が今も昔も、「誰にも負けない」と心から言えるのは、「バイクを心から愛している」という点だった。
だれかれ構わず見せびらかしたいほどに包丁やフライパンを大好きでなくても一流のシェフになれるし、胸に抱いて眠りたいほどの愛をシューズに感じていなくても、陸上競技の金メダリストになれるのと同じように、レース自体はバイクが好きでなくてもできる。
だが、子供の頃に藤岡弘、さん演じる『仮面ライダー』を見て以来、私にとってのバイクは「乗り物」という範疇を超え、私が生きるための糧であり、人生全てを賭けるに値するほどの存在だったと断言できる。
それほどまでに私がのめり込んだバイクというものを、少しでも多くの人に理解してもらいたい、好きになってもらいたいという気持ちは日に日に大きくなっていった。
誰にどう思われようとも私がバイクを愛していることは変わらないし、「俺の背中を見て憧れる者がいたら付いてこい」と多くを語らないのも男の生き方として美しいかもしれない。当たり前のことだが、人生の全てをバイクに捧げるような生き方をあまねく広めて回りたいといった大それた考えを抱いたわけでもなかった。
だが、「同好の士」は増えたほうが──もう少しビジネスに相応しい言い方をするならば、「市場」は拡大したほうが──“楽しい”に決まっているのだ。
「当事者」として顧みるべきことがあるのを認識しつつ、私には、強い危機感を抱いていることがあった。それは、バイクやレースが、人々にとって憧れでもなんでもなくなってしまっているのではないか──というものだった。
交通事故をきっかけとしてシートを失い、私がレース活動の舞台を日本からアメリカへと移した1993年頃を境に、日本のレーシングシーンからは次々にスポンサー企業が撤退をしていった。企業が一般消費者の社会にコミットするにあたって、バイクというものが変わらず魅力的な存在であったならば、そんな事態にはならなかっただろう。事実、1993年に始まったプロサッカーリーグ「Jリーグ」は盛況で、ビジネスとして立派に成立していたのだから。
レースは、「走ることが大好きな人間がサーキットを走ると、お金が懐に舞い込んできて、また走れるようになる」といった「夢のビジネス」ではなく、観戦をする側が「応援したい」と思い、サーキットに足を運ぶ、あるいはテレビを視聴するようになり、さらには「また行きたい」「もっと知りたい」というサイクルが生まれた時に初めて成立する「興行」に他ならない。私がアメリカで痛感したように、「与える/与えられる」の関係が釣り合わない限り、ビジネスにはならないのだ。
レースの関係者は口々に「もっとレースに足を運んでもらわなければ」と話してはいたが、「速く走りさえすれば、それを見ている人も楽しいだろう」といった考え方はいまだ根強いように見え、日本のレースは早晩死に至るのが明らかだと思えた。
-
前の記事

トップを走れ、いつも vol.10 1998年、新たな人生を求めて トップを走れ、いつも
-
次の記事

トップを走れ、いつも vol.12 (最終回) 得手に帆あげて トップを走れ、いつも