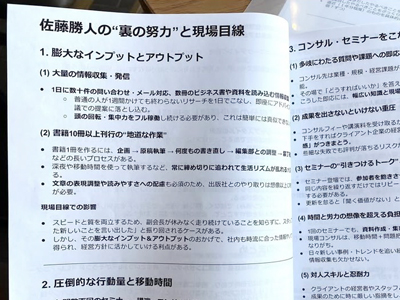リモートは権利だ!

かつ、長期トレンドになりつつある。同調査によると、新型コロナ収束後も在宅勤務――調査の表記は「テレワーク」だが、在宅勤務のことだと思われる。上記初出も同様――を続けたい人は53.2%。20代と30代では6割を超えている。そもそも政府が「出社7割減」を要請しているわけで、各産業分野ではリモート化のニーズが立ち上がり、マーケットもそれに向けて動いている。波はしばらく止まりそうにない。
ドイツでは4月、フベルトゥス・ハイル労働社会相(日本における厚生労働大臣)が「在宅勤務権」構想を打ち出した。ドイツでは3月中旬以降、国内の全労働者の4分の1にあたる推定800万人が在宅勤務を行っていて、相は「ウイルスの脅威が去った後も、在宅勤務を望み、それが可能な職業であるなら、誰でも自宅で仕事ができるはずだ」として、早ければ今秋にも法案を提出する可能性があるという*2。
5月にはイギリス政府も在宅勤務権の法制化を検討中と報じられた。もともと欧州では「在宅勤務」が労働者の権利として扱われており、フィンランドでは今年1月、労働時間の半分以上を自宅を含む好きな場所で働ける法律が施行された。オランダにいたってはすでに2016年、自宅を含む好きな場所で働く権利を認める法律が施行されている。建て付けとしては「労働者が企業に在宅勤務を求めた場合、企業は拒めるが、その理由を書面などで説明する義務がある」*3となっており罰則規定はないとはいえ、在宅勤務が法的な権利概念になって出てくるあたり、労働組合が機能する社会ならではと思わせられる。
現象論的に言えば
最初からリモートになり得ない職種と労働者は「エセンシャルワーク」「エセンシャルワーカー」という分類が社会的に認知されたし、そうではないのにまだリモートになっていない労働者は会社が未対応なだけで、本人の責任ではないからだ。そうして最後に残る1タイプ、つまり「リモートワークになったけどうまく働けていない人」に話を振ってしまったときも、出てくる地雷はせいぜい、「家族がうるさいし、つい冷蔵庫のおやつに手が伸びて・・・」みたいな“トホホ系”ですむ。つまり現象論的に言えばリモート化は「人の口の端に乗りやすい」のである。
ともあれこれも看過すべき話ではない。家族がうるさくておやつに手が伸びて集中できなくてかえって疲れる。すべて在宅勤務の「現象学」の範疇だ。というわけで、以降は職業柄在宅勤務に精通する者として一考を講じたい。
在宅勤務の課題
2位のテレワークでできない仕事とは、エセンシャルワークのそれではなく、他でもよく例にあがる「ハンコを押すために出社」みたいな、“アナログの呪い”のことだろう。4位と8位は要は同じ課題であって、1位の運動不足も厳密には勤務の課題ではないが、とりあえず一緒にしてよい。
残るは5位「仕事に集中できない」だが、これは家族がうるさかったり冷蔵庫が誘惑してきたりといった理由以外にも、何か原因があるのではないか?
「仕事のなかの曖昧な不安」
筆者の理解では、これらは大きく分けて二つの「不安」につながっている。
一つは精神科医でサブカル批評家の斎藤環氏が「人は人と出会うべきなのか」*4で書いた「臨場性」にまつわる不安である。同氏はこの論考で、臨場性は「暴力」であり、「欲望」であり、「関係」であると定義し、そのわけをそれぞれ説明している。
本稿タイトルの「現象学」は氏の論考を意識していることは後注のリンクから一読いただければおわかりだろうが、その文脈によせて解釈すれば、在宅勤務で相手の気持ちがわかりにくいという「不安」を感じる人、相談しにくいと思われていないかと「不安」を感じる人というのは、臨場性の「暴力」に飢えているのだ。あるいは、少なくともその「暴力」を頼みにできない状況に居心地の悪さを感じているのである。不安から課題に戻って5位「仕事に集中できない」も、斎藤氏の言う「暴力‐欲望‐関係」のトリニティを欠いた状態と解釈すれば、すんなり納得できる。
大きく分けた「不安」のもう一つは、在宅勤務は労働時間規制の基準がまだ曖昧であることだ。これは2位「仕事をさぼっていると思われないか」という「不安」に関連する。
労働政策研究・研修機構労働政策研究所長・濱口桂一郎氏によれば、「在宅勤務もかつては原則この事業場外労働で(引用者注:事業場外労働の見なし労働時間制で)やっていたが、なまじ情報通信技術が発達しすぎて、一挙手一投足までいちいちコントロールしようと思えばできるようになってしまったため、むしろ通常の労働時間規制を適用するのが原則になってきてしまった」*5。つまり出社勤務(事業場内労働)で9時5時の働き方をしていれば、雇用主あるいは指揮監督者によって、在宅でも9時5時の働き方を自明視されるということである。
しかしこれは在宅勤務が本来持つ生産性向上の効果を阻害する措置に他ならない。このことは、卑俗なシミュレーションながら出社勤務との比較で容易に推測できる。
会社に来れば、目を開けてパソコンの前に座っていれば“中身”は寝ていても稼働中と見なされる。そこには残業の予感はあっても労働強度の観念はないだろう。だが、在宅勤務ではモニターのマウスの動きやカーソルの進み具合によって、雇用主や指揮監督者は従業員の稼働状況を逐一可視化して把握できる。ログ解析で従業員個々の特性を導き出し働き方の(=働かせ方の)最適化を進めるツールも開発されている。オフィスの従業員には倫理上やりにくいそれらの監視・解析も、場外労働の実態を正しく把握するため――ひいては評価査定を間違いなく行うため――との建前でならやりやすいに違いない。
本質的な疲れ
自宅空間にはプライベートのリズムがある。自宅にいて事業場内の時間配分・リズムで稼働することはそれだけでタフなことであり、プライベート空間に事業場内の時間配分・リズムを持ち込まれることの屈辱――臨場性をともなわない「暴力」!――たるや、精神を蝕むのに充分だ。
濱口氏は『労基旬報』6月25日号に「今後はむしろ、裁量労働制の見直しとも絡みますが、業務の遂行手段と時間配分の決定等について使用者がいちいち指示しないことに着目する形で、テレワークに対する労働時間規制の在り方を見直していく必要があるように思われます」と書いている。筆者も完全に同意する。マウスやカーソルの動きを解析して労働強度を積み増すなど、まるでチャップリンの『モダン・タイムス』の現代版ではないか。あれから84年も経つというのに。
*1 「新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」
*2 「労働者の「在宅勤務権」構想 ―新型コロナウイルスを契機に」(労働政策研究・研修機構)
*3 「在宅勤務が標準に 欧州は法制化の動き、米は企業主導」(日本経済新聞 2020/6/12)
*4 「人は人と出会うべきなのか」(note 斎藤環 2020/05/30)
*5 「「ジョブ型」の典型は、アメリカ自動車産業のラインで働くブルーカラー労働者である」(hamachanブログ 2020/6/20)
(2020.7.1)