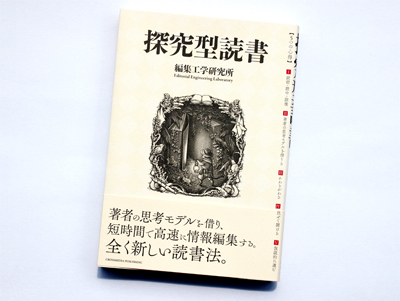そっちの面が前に出ている間は本能的に買い控えるタチなので、自分の直感を信じるならば、本書を選んだのはそういう売り方の旬が終わったか――いいことだと思います。著者にとっても――、「コロナが消費をどう変えるか」というテーマ自体に惹かれたか、どちらかだと思います。
「どちらかだと思う」は本当はレトリックに淫した言い方で、実際は両方です、たぶん。だからこそAmazonのレビューにある「期待外れ」という趣旨の指摘も理解できる。本書単体で、とはつまり「三浦展本」なるものを予期せずに一書籍として読むならば、読み物としての魅力を本書に期待すると間違います。著者もその線を意図していません。巻頭第一言にこうあります。
「本書は団塊ジュニア、あるいは氷河期世代、ロスト・ジェネレーションなどと呼ばれる世代、またゆとり世代、さとり世代、平成生まれなどと呼ばれる現在のほぼ20代の若者について、階層の違いによって、彼らの意識、行動、特に消費行動にどのような違いがあるかを調べることを主眼として企画された。」(序章 p16)
要はあくまで調査レポートであり、著者の専門であるマーケティングの資料です。そのままだと一般読者は興味を持てないから新書にしたまでで、「社会をもっとこうしよう」とか「このままではよくないんじゃないか」とかいった問題意識を発展深耕させたい人には、他に適した本があると思います。評者としては、「コロナが消費をどう変えるか」という予測例が得られたので充分でした。
そのうえで、本書で印象的だったのは文体です。序章第1節「コロナ問題の本質」と221ページからの「あとがきにかえて」は、調査資料らしくない、逆に言えば読み物らしい魅力を備えた数少ない箇所なのですが、「この文体、誰かに似てる・・・」と思い当たったのが、投資家でブロガーの山本一郎さんでした。
それで何かを言いたいわけではない、と急いで付け加えないといけないあたり、山本氏もかなりキャラが立った書き手なわけですが、これらの箇所は一般読者の視点でもおもしろかった。「たしかに!」とか「それはどうだろう」とか、自分の考えに照らしていろんなことを思い巡らせながら読めます。おそらくどの読者もそうだと思います。結構ラジカルなことを言っているので、いろいろな立場の人が、それぞれの興味で読めるはず。
特に興味深かったのは、「あとがきにかえて」の章の第2節、「寄生地主の権益を見直せ!」の箇所です。「コロナが終息したとき、いったい日本から何軒の飲食店が消えているのだろう」と始まる229ページからの第1項、次いで230ページからの第2項では「あらためて私が思うのは土地、家賃というものの残酷さである」と続きます。
「あらためて私が思うのは土地、家賃というものの残酷さである。多くの店(テナント)が、日銭商売の自転車操業をしており、客足が止まれば売り上げは減少し、まず家賃が払えなくなって廃業するのだ。/オーナーのほうも大変なのだという報道も見たが、そうだろうか。自分で買った土地に自分でビルを建て、テナントを入れて長らく地元に貢献してきたというのなら同情もするが、テレビ報道で見る限り、投資のためにビルを買ったオーナー(個人か会社か、リートか何かは知らない)が、家賃が入らないと銀行に借金を返せないという事例が多かった。/だが投資をしてもうけようと思ったのだから株と同じで、暴落して損をしても自己責任である。だれも損失を補填してくれなくて当然ではないか。」
今回のコロナ禍では、家賃については特に議論が湧きおこりました。ここでの三浦氏を「借りる側」の代弁者の一人とすれば、「貸す側」を代弁した一人が山本氏です(参照:『BEST T!MES』4月23日「松田公太「コロナで客が来ないから」外食産業の家賃棒引き法の無法地帯」。note5月1日「こういう難局のために、現預金はある」)。
どことなく似た文体の、それぞれ際立った二人が、真反対の利益代表者みたいになって議論を戦わせる。もちろん実際は無関係な別々の言説で、評者の頭の中の空想ですが、ここにさらに精神科医で評論家の和田秀樹さんのような「相続税100%論」が入ってこようものなら、興味深すぎて夜も寝られません。今回コロナ禍で白日にさらされた国政の混迷、政治家のリーダーシップのなさも、相続で守られた世襲政治の行き着く果ての姿と解すればすんなり納得できます。
以上のような読み方を一般読者はしつつ、マーケティング業界、あるいはより広く供給側の読者なら、例えば130、131ページなどが参考になるはずです。
「旅行会社は、パリやローマに旅行してほしいが、平成世代が行きたいのはウズベキスタンかもしれないのである」(p130)
「私が古着に注目したのは1998年から2001年ごろだが、そのころマーケティング調査をして、若者は古着が好きですとリポートしても、企業側は、今ちょっと景気が悪いからでしょ、景気が良くなれば古着は買わなくなるでしょ、という反応であった。そう反応したのはバブル世代である。」(p131、132)
2つめに関しては耳の痛い読者もいるかもしれません。あるいは、それからもう20年前後経ったのだからさすがにそういう人は(=決済権者は)いなくなっているでしょうか。でも、この20年間多くの業界がやってきたことは、上の世代を守るための非正規雇用の促進であり、定年制の見直し(延長)であり、そのための法整備とサポート体制の拡充(パソナ?)でした。「あとがきにかえて」に戻って233ページラストにはこうあります。
「過去15年ほとんど株価が上昇していない重厚長大の古い企業が今も経団連の中枢であることも、この際問題視したほうがよい。」
評者はこの一文から、「ひふみ投信」のマネージャーでレオス・キャピタルワークス社長の藤野英人さんの著書『投資家が「お金」よりも大切にしていること』(星海社新書)を思い出しました。5年と半年前の小欄で取り上げた本だからです。その238、239ページの要約が下記。
「経団連に関して、会長および副会長企業18社のうち、最近10年間(2002年9月~2012年9月)で株価が上がったのは6社にすぎない。2社が微減、残り10社はボロボロ。彼らは“失われた10年”と言い、「この10年、日本はダメだった」と言うに決まっている。環境のせいにしないと、自分の経営者としての無能さを世間にさらけ出すことになるからだ。しかし事実は、東証二部の企業株価総額は10年間で67%のプラス、一部も66%の会社で株価がプラス、かつ倍になっている。それなのに、株価を大きく下げた会社の経営者たちをリーダーに選ぶのは、真面目な態度だろうか?」
藤野氏がこう書いたのは2013年の2月です。日本はそれから一個も変わらないまま来たのでしょうか。