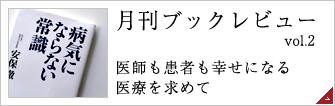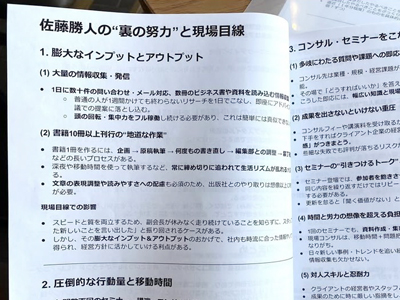ただの「満足」では足りないと言っているのです。あなたの商品、会社、お店が売れ続けるためには、満足の上をいく心に響く何かを提供する必要があります。それで初めて、お客さんの「記憶に残る」ことができるのです。
――第一章 スーパーより高い野菜が通販で売れる謎 より
本書を読んでドキッとするのは、たとえばこんな箇所だ。「顧客満足(CS)というマーケティング用語があります。顧客満足は、1980年代にアメリカで提唱され、しばらくして日本にも導入されるようになりました。」・・・現在多くの企業や商店で金科玉条とされる「顧客満足の追求」が、歴史的にはさほど古い概念ではないこと、以前はもっと尊重される軸が別にあったことを示唆するこのくだりは、専門家が通史を踏まえて語ると怖い例の一つである。時々こういった一節に出会ってパラダイムチェンジを図ることは有効だ。普遍性に根ざしていたつもりが案外そうでもなかったという気付き=頓悟は、“既存の・できあがった・停滞した”世界を去るうえで、常に最良のキッカケになるからだ。
*
冒頭で著者はこう断っている。「タイトルを見て、ちょっとムッとして手に取ったあなた! ゴメンナサイ。この本は、決して“物を売る商売”をバカにするという意図で書かれたものではありません」。続く文もふくめてタイトルのニュアンスを意訳するなら、「こんないい商品を持ってるのに、なんでそんな売り方しちゃうの! もう、バカバカ!」といったところか。著者の川上徹也氏は大手広告代理店出身のコピーライター・CMプランナー。商品が持つ〈物語〉――生産者の想いや顧客とのエピソードからつくる付加価値――をマーケティングに活かす「ストーリーブランディング」の手法で知られ、2008年出版の『仕事はストーリーで動かそう』(クロスメディアパブリッシング)以来、17冊のビジネス書を上梓している。本書は氏がこれまでに書いてきたストーリーブランディングの解説の集大成という位置づけである。
実のところ、書かれてある手法や考え方そのものは、さほど目新しいとは感じない気がする。それはつまり、これらの手法があまりに効果的だったせいで速やかに普及が進み、もはや提唱者が誰かということを離れて私たちに知られているということなのか、それとも、2008年よりもっと以前から同種の手法は大なり小なり街場の商店主たちによって実践されており、著者の功績はむしろ、それら優れた民間知を発掘し、体系づけた点にあるということなのか。どちらなのかはわからない。しかも、事態としてはまったく違う両者を区別することにさして意味がないと思えてくるのは、当の手法が区別を要さない水準に根ざしているからだろう。つまり、普遍に。
「ネーミングの力」「体験を加えて付加価値を生む」「〈物語〉を使う7大メリット」「大義を売る」・・・などなど、具体的なアプローチの詳細は実際に本書を買って読まれることをお勧めする。きっとおもしろいはずだ。と同時に、一つひとつ実際のエピソードもあげながら詳しく解説していく著者の、心底楽しそうな様子が印象に残るはずだ。本書第五章では新幹線の車内販売で通常の4倍売るカリスマ販売員(日本レストランエンタプライズ元社員の茂木久美子さんか、同社アドバイザーの齋藤泉さんのことと思われる)のエピソードと一緒に、「お客さんとラブラブな状態になる」ことの力が紹介されるが、川上氏もきっと、大企業の資本力に押されつつも知恵と工夫と行動力でお客を喜ばせ、愛されている地方の中小企業たち、街場の商店主たち、町工場のオヤジさんたちが大好きなのだ。その愛があればこそ、彼らの商品に眠る〈物語〉とその活かし方を見つけることができたのである。
*
本書の最終章は「結局すべては『人』なんだ、という法則」。著者はここで“商品に人をプラス”する考え方を紹介する。いわく、これがないと〈物語〉も意味をなさないと。なぜか。人にしか連れてくることができないものがあり、それが〈愛〉だからだ。なるほど、商品に顧客が満足し、売り手がそれに満足した後もなお双方の感情が「もっと!」と伸びるなら、その先は確かに〈愛〉の領域である。CSもここで初めて普遍に届くのだ。
![]()