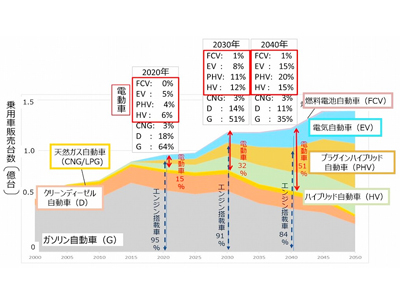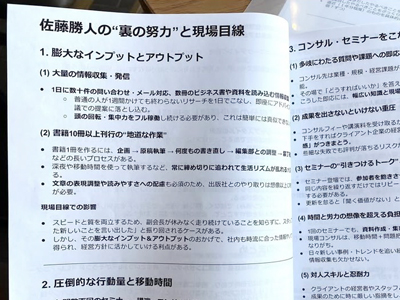でも、分業を初めて“発見”したのは『国富論』のアダム・スミスです。スミスは裁縫に使うピン(針)ができあがる過程を例にとって分業の概念を次のようにイメージしました*1。
今仮に1本のピンを全部1人でつくるとしたら、鉱山から鉱石を掘り出して金属を精錬し、細長い金属棒を鍛造して決まった太さと長さの針金に加工し、頭を付けて胴の表面を磨いて先端を研いで完成させるまで1年がかりだろう。しかし、もし既製の針金が手元にあってそこから始められたら、1日20本しか完成させられなくても年間300労働日で1年に6000本のピンがつくれる。鉱石の掘り出しは鉱夫に、金属精錬と鍛造は鍛冶屋に、針金からピンにする仕事はピン職人に、それぞれ分業することで、ピンの供給が増え、消費者は格段に安くピンを買えるようになり、各業は売り上げが増大して業主はそれぞれの労働者に格段にいい手間賃を払えるようになる。――これが「分業」の概念です。
本書は「リソース効率とフロー効率という二つの効率を向上させていかに生産性を上げるか」を説いた本。ここで「二つの効率を向上させて」は、ついつい「二つの効率をうまくバランスさせながら」と解釈したくなりますが、それは間違いです。
本書が唱える「リーン」とは、1988年に専門誌『スローン・マネジメント・レビュー』に載った、さまざまな自動車メーカーの生産性を比較した記事「Triumph of Lean Production System(リーン生産方式の勝利)」で初めて注目され、西側諸国で発展し、今や世界で最も広く浸透している経営概念の一つだそう。きっかけになった記事の著者いわく、生産システムには規模の経済と先進技術によって担保された「堅牢なシステム」と、在庫が少なくバッファがわずかで単純な技術を用いる「脆弱なシステム」があり、後者のシステムを採用するメーカー(例えばトヨタ)のほうが品質も生産性も高くなるとのこと。
「リーン(贅肉のない・痩せた)」という語は「脆弱な」がネガティブに響くので代わりに使った語だそうで、今なら「柔軟な」とか「機動的な」とかが近そうです。しかし本書によれば、それでは「リーン」の本質はつかめないそう。
リーンは二つの効率のうちフロー効率を常に優先します。リーンにおいてフロー効率とは、「顧客ニーズを早く満たすこと」を第一義に据えることで、直接それに関係しない二次的業務が生じないようにし、生じれば徹底的に排除し、全体効率を高める発想のこと。この世界線ではフロー効率を向上させようとすれば必然的にリソース効率も上がるとされています。「二つの効率を向上させて」を「二つの効率をうまくバランスさせながら」と解釈するのは間違いだというのはこの意味です。
リソース効率については第一章で次のように述べられます。
「昔ながらの意味で「効率」と言うときには、リソースをできるだけ有効に使うことを意味している。過去二〇〇年以上、産業はおもにリソースの活用を高めることで発展を続けてきた。その基本原則の一つは、仕事を小さなタスクに分け、それらをそれぞれ異なる働きをもつ個人や組織にやらせることにあった。/もう一つの原則は、規模の経済を見つけること。小さなタスクをまとめ上げて、個人が、組織の一部が、あるいは組織が全体として、同じタスクを何度も繰り返し行うことでリソース効率を高める。/今も昔も、リソースを効率的に使うことが、効率を高める一般的な手段だ。今もこの考え方にもとづいて、さまざまな産業や分野で組織がつくられ、制御され、管理されている。」
(第一章 リソース重視から顧客重視へ p28、29より一部省略して引用)
つまり「リソース効率とは分業だ」と言っていいでしょう。スミスのピン職人の描写は正確にリソース効率の考え方に対応します。ただ、吉本隆明によるとスミスの本当の“発見”は分業そのものにではなく、「ピン製造業者や(評者注:それぞれの業に従事する)労働(者)のあいだから哲学(者)を発見した」ことにあります。下記引用。
「すでに知られていて、またすでに一つの特定の目的に適用された諸力を、もつとも有利な方法で使用することは、才能ある技術家の能力をこえるものではない。しかし、全然知られていず、また類似のいかなる目的にもこれまで使用されていなかつた、あたらしい力の使用をおもいつくのは、単なる技術家が生れながらにもつているよりも広汎な思考と観察を有する人々にのみ、なしうることである。ある技術家がそのような発見をするならば、彼はそれによつて、自分が、表面上の職業は何であろうと、単なる技術家ではなくてほんとうの哲学者であることを、しめすのである。」
(『ハイ・イメージ論Ⅱ』p9、水田洋訳『国富論草稿』の引用より)
本書が説くリーン――全面的にトヨタでの研究によっているので実質トヨタの理論――では、各工程の従事者は全員がフロー全体を俯瞰し(見える化)、顧客ニーズの充足を目指してフロー効率を実践しています。しかも、生産もサービスも現実の活動である以上は100%の効率が実現することはありえないので――人間の不調、機械の故障、天候災害、etc.――、フロー効率向上の取り組みには原理的に終わりがない。これが有名な「カイゼン」です。トヨタイズムの要として海外でも知られる「Kaizen」が一種の宗教的ニュアンスを帯びるのは、この永久運動が理由でしょう。
本音を言えば、リーンが想定する労働者像は、スミスが見出した哲学者の部分をうまいこと業主に接収された労働者だ、と僻みたくなる気持ちが起きなくはありません。スミスが“発見”した労働者像の飛躍と輝きが、たかが企業のオペレーション戦略の話に矮小化されてしまったような。
とはいえそれは評者の個人的なないものねだりです。本書は経営を志す人にとって、「そんなの(本来なら)当たり前じゃん」と思うことを論理で記述したらまさしくこうなる、という意味で、それこそ小学校時代の教科書のような意味を持つはずです。目指されていることはそれくらいシンプルです。でも、マルカッコの(本来なら)がどうやっても残るから、こうやって本になるのでしょうね。
*1 『ハイ・イメージ論Ⅱ』(吉本隆明著・1994年・福武文庫)の「拡張論」よりp6~44を参照