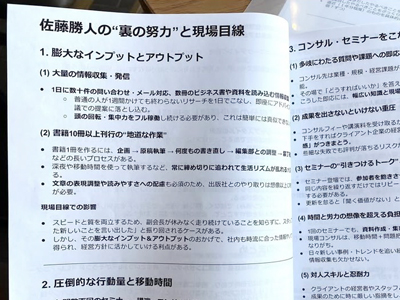vol.5 1994年3月 デイトナを、2ラップ
奇跡の生還、しかし・・・
2週間にもわたる「デイトナウィーク」で私にできたのは、ホテルの部屋で芋虫のように横たわることだけだ。突如として空席になったトップチームのシートには、当然のことながら様々なライダーが売り込みをかけてくることとなる。クラッシュから3日目、ほとんど動かない体を車いすに預けてパドックへと出向いたときには、すでに私のシートは失われ、栄光のゼッケンナンバー1を付けたマシンは、他のライダーが走らせていた。
「お前のバイクは速すぎるな」と、コーリン・エドワーズが声をかけてきたのを覚えているが、バイクに乗ることはもちろん、歩くこともままならぬ私には、何の慰めにもなりはしない。
アメリカで長くレースをしたいと思ったら、絶対に転ばないようにしろ。バイクを壊す、治療費がかかる、そんなライダーがアメリカでは、最も嫌われる──全身を襲う痛みに悶えながら、アメリカに渡ってきてすぐの頃、モトリバティのオーナー、サムに言われた言葉を思い返していた。
現地のブリヂストンスタッフの説明するところによれば、あのタイヤバーストはタイヤそのものの不具合によるものではないという。なるほど、ブリヂストンタイヤならばそうに違いない。だとすれば、パドックの路面上の異物、あるいはコース上のデブリといった、その他の要因によるものとなるが、それが何なのか・・・いや、本当にコース上にそんなものがあったのかどうかさえ、結局明らかになることはなかった。
なんと理不尽なことだろう・・・。原因さえわからぬまま、私は「転倒した愚かなライダー」として認識され、ようやく掴んだトップチームのシートを失い、おそらくこのシーズンを棒に振る。多くのバイカーたちが青空のもとに集う、華やかでエネルギッシュな空気とは対照的に、私の心は沈んでいくばかりだった。
失われない恐怖の記憶
不幸中の幸いと言うべきか、スーパースポーツ600クラスに限り、私はエリオン・レーシングのシートに復帰することができた。「結果が全て」のアメリカのレース界において、私をシーズン最後まで走らせてくれたケビン・エリオンにはどれだけ感謝をしてもしきれないが、状況は最悪だった。
どんなビジネスでも、挑むことに恐怖を感じてしまったら前に進むことはできない。だというのに、私の全身は「恐怖」に支配されてしまっていたのだ。
レーシングライダーがこれに打ち勝つためには、とにかくバイクに乗り続けることしかない。いかにクラッシュが恐ろしいものであっても、そこで負った傷が痛むものであっても、コースに出続けさえすれば、いくつかは「自分はできる、まだやれる」という要素を見いだすことができる。そうしているうちに、恐怖など忘れられるものだ。
だが、今回ばかりはそうも行かなかった。ベッドで寝返りを打つたび、バスルームで、キッチンで、水が傷口に触れるたび、あの恐ろしい経験が、強烈なリアリティを持ってよみがえってくるからだ。
その後のシーズンについては、何も語るべきものは無い。デイトナを、2ラップ。それが1994年という年だったのだ。
──スーパースポーツ600クラス・ランキング9位。シーズンが始まる前に思い描いていた展開とは180度異なるそれが、最終リザルトとなった。
*
「反省はしても、後悔はしない」。のちにPGA(日本プロゴルフ協会)会長、倉本昌弘さんの言葉を記事で読んだとき、同じプロアスリートとして、非常に共感したものだ。地獄のような1994年から再起を図ることができたのは、この気持ちがあったからに他ならないからだ。
NASCARターン3でステアリングが振動した瞬間に、その先にあるリスクを感じ取り、スロットルを戻すべきだった。これは、私が反省すべきことだ。だが、それを悔やんだところで時間は戻っては来ない。「できなかったことができるようになる」ことと同じくらい、「できなくなってしまったことが、再びできるようになる」ことは楽しいものであるはずだ。私はレーシングライダーとして、何度でも立ち上がり、トップを目指し続けなくてはならない──。
だが、そんな気持ちを胸に、ふたたびレースに挑めるようになるのは、まだもう少し先のことだった。
──第6回に続く
(構成:編集部)
「トップを走れ、いつも」
vol.5 1994年3月 デイトナを、2ラップ
(2014.9.24)