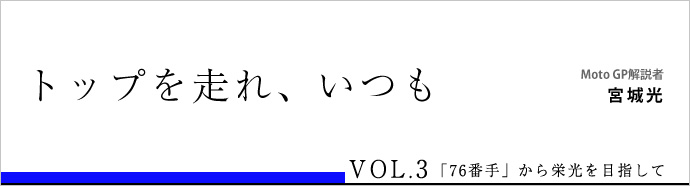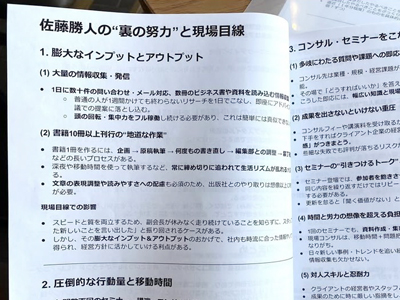vol.3 「76番手」から栄光を目指して
2度目の奇跡を起こせるか
「おう、お前の言う通りにしてやる。ちょっと待ってろ」
「スプロケットをショートにしてくれ」という何度目かの私の要求に、メカニックのアール(AMAのトップライダー、ミゲール・デュハメルのマシンセッティングも務める超一流のメカニックが、私のためにヘルプでチームにジョイントしてくれていた)は嫌な顔ひとつせずに応じた。
前日とは違い、コース上に強い風が吹いていた。ホームストレッチは追い風。バックストレッチは向かい風。こうしたシチュエーションでは、スプロケット(チェーンの回転を後輪へと伝える歯車)の丁数ひとつが大きく勝負を分けることになる。これを大きくして加速重視にするか(「ショート」)、小さくして最高速重視にするか(「ロング」)、延々と迷い続けていたのだ。
あれほどの逆転劇の後でも、スタートは相変わらず76番手。いったい、どちらが私に2度目の奇跡をもたらしてくれるのか。スタート時刻が迫る。グリッドへ向かってバイクを運ぼうかというそのとき、私は決断した。
「やっぱりロングにしてくれ」。
「わかった。すぐにやる」
アールは、熟練のメカニックらしい手慣れた手つきでスプロケットを付け替え、私をグリッドへと送り出した。
チャンスのきっかけにもなったテストで私を指名してくれたブリヂストンの藪田さん、ケビン・エリオンにクレッグ・エリオン。私が最高の結果を残せるよう、尽くしてくれているアール。モトリバティのサムにも。彼らの「応援」に報いるのだ。
抜く、抜く、抜く
レーススタート。
既に「ファーストウェーブ」のトップ集団は見えなくなっていた。スプロケットをロングにするという選択をしたことで、私が採らなくてはならない戦略は、「自分以外の全てを利用する」ということだ。抜いても抜いても前が居るのだから、最高速を重視した代償として鈍る加速は、前を走るライダーの背後にぴったりと付くことで空気抵抗を減らして補うわけだ。
インフィールドセクションを抜けて向かい風のバックストレートへ躍り出る。最高速重視のセッティングの弊害で、パワーが足りなくなり、すぐ前を走っていたライバルのテールが遠のきかける。
オーバルセクションの30度バンクでは、「すり鉢」の上から下まで、4台も5台ものバイクが横並びになっていた。どのライダーの後ろに付くべきか? わずか12周の間に75台を抜かなければならない私には、それを吟味する時間は無い。コンマ1秒すら惜しい。
セオリーにとらわれず、利用できるライダーがいるラインを縦横無尽に駆け回り、後ろに付き、そして抜いた。夏の間に厳しいトレーニングを積んだ私には、このタフな状況で瞬間的にあらゆる選択肢のリスクを的確に判断する力があった。
通常のサーキットとは異なり、バックストレッチでサインボード(ライダーの順位やライバルとのタイム差をチームが知らせるためのボード)を出すのがこのデイトナの特徴だが、もはやそんなものは何の役にも立たない。今何位なのかはわからないが、前にバイクが居る限りはトップではないことだけは確かだ。12周にわたって、とにかく、抜いて、抜いて、抜きまくった。
ファイナルラップ、メインストレッチへと戻る、オーバルセクションのターン5。スプロケットをロングにしていたのが幸いした。スリップストリームから飛び出した私のCBR600は追い風を受け、先行するマシンよりも加速の伸びがわずかに良かった。イン側を抑えるライバルを、アウト側から被せるようにして抜き、フィニッシュ。
まだ何100メートルも先に、ぶっちぎりの1位がいるのではないか・・・そんな考えも捨てきれなかったが、結果的にはそれが最後の1台だった。
私は、「75台抜き」を2日連続で達成したのだ。
プロフェッショナルとは、どうあるべきか
アメリカ人に対して、「プロのレーシングライダーである」と自己紹介をすると、かならずと言っていいほど返ってくるのが「お前はチャンピオンなのか?」という言葉だ。そこに、日本で美徳とされるような遠慮会釈といったものは無く、「プロフェッショナル」という言葉が重い意味を持っていることがわかる。
日本で10年以上「プロのレーシングライダー」を続けていたが、渡米したことで、「プロフェッショナルとはどうあるべきか」を、もう一度見つめ直すことができたように思う。
いっぽうでアメリカという国が面白いのは、結果というものに非常にシビアであるということとセットになって、「一生懸命やっている姿は見ているし、結果を残せば手をさしのべる」というメンタリティが浸透していることだ。
目標を立て、最も効果の出るところに手持ちのリソースを集中させ、結果へとつなげたのは、プロフェッショナルのレーシングライダーとして誇ることができる、私の大切な経験だ。一方で、その姿を見てくれていた人、私に賭けてくれた人の存在というのも、忘れてはならないと思っているし、「全力で挑み続ける人」を決して見逃さず、手をさしのべられる人間でありたいとも考えている。
――第4回に続く
(構成:編集部)
「トップを走れ、いつも」
vol.3 「76番手」から栄光を目指して
(2014.8.27)