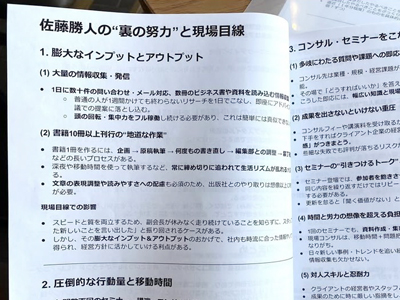2兆円? 1兆円? 5000万円?

aquamarine/ PIXTA
ただ、国土交通省のまちづくり関連の資料を見ると、歩数から効果を試算する際の原単位には研究機関ごとにばらつきがあり、例えば国立国際医療研究センター病院の糖尿病・代謝症候群診療部は0.0015円/歩/日としている。「糖尿病を中心とした疾患の発症リスク低下」の観点からは医療費抑制効果は約40分の1の5000万円に留まるということだ。
もっと日常に寄せて「1日あたり歩行量(歩数)が1歩違うと年間の医療費(入院外医療費)がどれだけ変わるか」で見た慶応義塾大学経済学部の原単位は0.030円/歩/日。一般の感覚からはまずは外来にかからなくてよくなることが一番の養生なのだから、抑制額は0.030円で計算した約1兆円と思っておくのが穏当かもしれない。それも全世界の過去の総額だから国内での年間の抑制額はもっと減る。いずれにせよコピー的な数字は冷静な態度で聞くほうがよさそうだ。
これを言うのは何も上げ足取りではまったくなく――石原氏もつかみで言っただけのはずだ――、医療の話題はさまざまな見方、基準が錯綜するので短絡に走るのは危険だということを、自戒もこめて強調しておきたいからである。そのうえで、今年がその元年になると言われているデジタルセラピューティクス(DTx)について考えてみたい。
デジタルヘルスとの違い
承認がおりて保険適用になれば「依存の治療に役立つ」は「依存を治療する」と書けるが、現時点ではまだだ。そしてこの薬事承認の有無が、デジタルセラピューティクスをデジタルヘルスと分ける境目である。治験で医科学的に治療効果が証明され薬事承認を受けたものが前者。症状の改善・予防や健康増進につながると一般に思われているものが後者。つまり「ポケモンGO」はデジタルヘルスの範疇に属する。リストバンド端末の普及にあわせ近年増えた睡眠管理アプリもデジタルヘルスの一種である。
睡眠関連のデジタルセラピューティクスでは、不眠症治療アプリ「yawn(ヨウン)」が治験段階に入っている。開発元は医療機器ベンチャーのサスメド社。サスメドは“Sustainable Medicine”の略だ。諸外国では不眠症治療には基本的に認知行動療法を第一選択とするのに比べ、日本は同療法による治療が充分にできる環境になく、人口当たりの睡眠薬処方量がアメリカの6倍になるという。「yawn」は認知行動療法をアプリで行うことでコストとマンパワー両面で非薬物療法のハードルを下げることを狙う。向精神薬の多剤処方を国も問題視する今、最も注目されているデジタルセラピューティクスの一つと言えるだろう。
医療費の是非と談合疑惑
この点については、「今の日本は極端に医療費抑制の話に寄っている」とする津川友介氏の冷静な指摘がある。津川氏はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)医学部・公衆衛生大学院助教授で医療政策学と医療経済学の専門家。筆者の管見の限り最も信頼できる医療政策関連の論者である。また、出典は2006年とやや古いながら、医療費抑制を言うのなら諸外国に比べて高過ぎる公定薬価と医療材料価格の見直しが先だとする出月康夫氏(故人・日本外科学会名誉会長)の指摘もある(外科系学会社会保険委員会連合発行「外保連ニュース」第5号)。
薬価をめぐっては昨年11月も大手医薬品卸4社の談合疑惑が発覚し、公正取引委員会が強制捜査に踏み切ったばかりだった。談合(現時点では疑惑)が生まれた背景には、薬を安く売ってほしい病院と高く買ってほしい製薬メーカーに挟まれて卸が薄利多売を強いられている現状があるようだ。診療報酬の引き下げで病院や診療所が困窮するにつれ卸が安売りをお願いされる事情は患者の立場からも察しやすいとして、製薬メーカーから卸への高値買いの要求も、相当なものがあったのではないか。談合疑惑発覚後の12月に日本製薬工業協会が発表した「薬価制度改革について」は、「平成30年度の薬価制度の抜本改革は、薬価の引き下げに偏った改革であり、製薬企業に与える影響は多大なものでした」と冒頭から恨み節で始まっている。
“ポケットのなかの健康”
「Digital Therapeutics、特にモバイルアプリやインタラクティブゲームには、患者、医療機関、それらのソリューションを提供する企業にとって、それぞれに大きなメリットがある。患者にとっては、自身の身体を侵襲することなく、吸入や注射といった作業や、痛み等の副作用から解放され、逆に楽しみながら治療に参画できるメリットがある。一方、医療機関やDigital Therapeutics を提供する企業等にとっては、アプリやゲームを通じて患者と常につながることで、患者の状態をタイムリーに把握し、詳細なデータを確認できるという利点がある。‥略‥データを媒体に患者、医療機関、ソリューション提供企業がつながることで、アプリ・ゲームのコンテンツやユーザーインターフェースを改良するサイクルを素早く回し、ひいては治療成績をあげていく。これは「売り切り型」の医薬品や一方通行の医療では実現困難な“Learning Healthcare”の考え方にも通じるところがあり、医療のパラダイムシフトにおける患者中心の医療の実現を考えた場合、医薬品企業にとっても重要な選択肢になりうる可能性を秘めているだろう。」(「ポケットのなかの健康 ~ビデオゲーム、モバイルアプリを用いたDigital Therapeuticsの臨床試験状況~」p55より)
“ポケットのなかの健康”とは味わい深い表現だ。ただし、スマホが眼鏡型デバイスに取って代わるまでは、立ち姿勢と座り姿勢ではストレートネックに、寝転んだ姿勢では肘部管症候群に、気を付けるよう!
(ライター 筒井秀礼)
(2020.2.5)