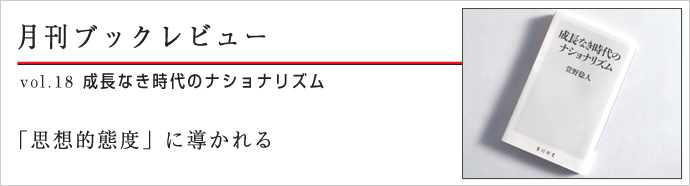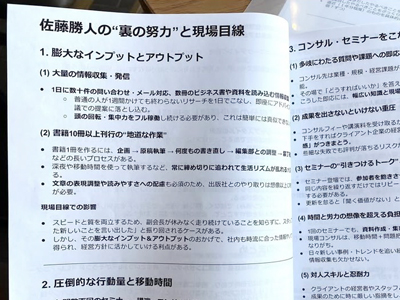批判する側は「底辺の人間が排外主義にむかっている」「自己疎外感や自己不全感をもつ人たちが他者への不寛容を拡大させている」といった根拠のない思い込みにもとづいて、福祉を手厚くすれば排外主義は収まると考えてしまう。その発想が実際には「パイの縮小に対する危機感」と対立し、排外主義の担い手をよりいらだたせてしまうことに気づかずに。
――第五章 ナショナリズムを否定するのではなく、つくりかえること より
11月2日、厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会において、介護休業中に支給される介護給付金について現行の「賃金の40%」を引き上げる方針が話し合われた。50、60、67%の三案が出たうち、同月25日の会議において育児休業給付金と同じ67%にすべきという見解が示され、そのまま決まりそうな見通しだ。一気に27%の上げ幅は労働者にとっては朗報だが、財源はどうするのか。報道によれば「失業保険給付の減少で雇用保険財政に余裕があるから問題なし」という判断のようである。いっぽうで制度の利用率は15.7%にとどまっており、介護休業を取得しないまま介護離職してしまった人たちの理由は、トップが「制度がない(あるのを知らなかった)」で45%、次が「職場に仕事を代わってくれる人がいなかった」21%である。周知の不備と、人員体制の不備。ここを放置したまま「カネは増やす。以上!」で済ましてしまっては、行政、経営者ともに、怠慢のそしりを免れない。
*
著者の萱野稔人氏は1970年生まれの哲学者。フランス現代思想を専門に大学で教鞭をとりつつ、月刊誌『サイゾー』に2010年から「“超”現代哲学講座」を連載するなど若者向けメディアでも活発に発信を続け、旧来の「難しいリクツばかりで行動や人物が見えない」哲学者像を打ち破った論客の一人である。本書によるとナショナリズムの問題は萱野氏が哲学の道に進んだ大きなきっかけの一つだった。「当初は私もナショナリズムに対してとても批判的で、いかにナショナリズムを克服するかということを考えていた」(あとがきより)。
そんな萱野氏はしかし、フランス留学中の8年間、欧州における極右勢力の拡大を目の前に見ながら考察を進める中で、ナショナリズムへの認識と評価を大きく変えていったという。そうして帰国した2003年以降の日本はといえば、右傾化が始まり、極右団体の朝鮮人排斥運動がメディアをにぎわし、民族差別発言が「ヘイトスピーチ」として一般用語に入れられ、「反韓」「嫌韓」が出版界の売れ筋キーワードになっていく社会だった。しかも、状況を冷静に批判し、思い込みにかたよらないで現在の・現実の社会をただしてくれるはずの知識人たちは、国粋主義の偏狭さをしたり顔で憂いてみせたり、軍国主義復活を恐れるあまり頭からナショナリズムを全否定したりで、その多くが役割を果たせなかった。要は日本全体が和製英語としての「ナショナリズム」の枠内で考えてきたのだ。その中で本書の意義は、私たちのナショナリズム論議をめぐる不毛な対立やら中傷合戦やらといったあれこれを、言葉本来の意味のまっとうな政治原理としてのNationalismに戻し、矯正してくれる点にあると思う。
本書で萱野氏は「ナショナリズムの担い手」という言葉をよく使う。この表現には「(和製英語で考えている点はともかく)彼らもある一つの思想の担い手としてその存在を認めるべきだ」というニュアンスがある。存在を認めれば、相手の主義主張の背景にも、その大元にある危機意識にも自然に目が行く。そこから実効的な討議を始めようというわけだ。思想的態度とはまさにこういうことを言うのであり、それに導いてくれるのが哲学なのだろう。例えば村上春樹なら、この対極にある態度=ナショナリズムをめぐる左右双方の現在までの態度を、こんなふうに描くに違いない。
「ただね、僕がそれよりも更にうんざりさせられるのは、想像力を欠いた人々だ。T・S・エリオットの言う 〈うつろな人間たち〉だ。その想像力の欠如した部分を、うつろな部分を、無感覚な藁くずで埋めて塞いでいるくせに、自分ではそのことに気づかないで表を歩き回っている人間だ。そしてその無感覚さを、空疎な言葉を並べて、他人に無理に押しつけようとする人間だ。」(『海辺のカフカ 上』・第19章)
*
本書が慰安婦問題も靖国問題も戦後の謝罪問題も、さらには安保関連の96条改憲の問題まで内容に含むことは、目次からわかる通りである。一貫して指摘される背景は、「成長しか知らない資本主義が、成長しない社会に入る」という、先進各国が歴史上初めて見舞われている共通の危機だ。年金破たん、民主党政権の失敗、自民党政権による構造改革路線の行きづまり、小選挙区制の功罪、若者と政治のすれ違い、etc・・・。全てこの危機が根っこにある。とりわけ第四章の最後、ベーシック・インカムについて書かれたp202からp230までの箇所は、「パイが拡大しない社会という現実」を前にして私たちがいかにも陥りそうな――政府も無意識のうちに導きそうな――落とし穴に気付かせてくれる意味で、本書の白眉だと思える。冒頭に記した「カネは増やす。以上!」で済ますことへのけん制は、直近の行政トピックを材にとったこの箇所の要約的再現だ。全体はぜひ本書を精読されたい。隅々まで内容の詰まった一冊だから。
(ライター 筒井秀礼)
![]()