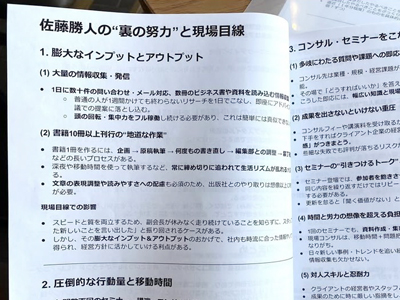生産緑地の2022年問題

蕎麦屋でもあるまいし、野党はいつまで支持稼ぎを、マスメディアはいつまで金稼ぎを、モリカケ問題でしたいのかと一般市民がいらだつ中で、予定会期最終日の衆議院決議でようやく成立した格好である。なお、国会そのものは空転の煽りを受け今月22日までの会期延長が確実になっている。
くしくも今年は都市における農業――都市農業――と切っても切れない関係の都市計画法が1968年に制定されてちょうど半世紀。この50年のあいだに都市の在り方と都市住民の生活スタイルが変わった。〈農〉の在り方も、営農者をめぐる経済的・社会的状況も様変わりした。昨年後半には都市緑地法等の一部改正を受けていわゆる「生産緑地の2022年問題」が話題になったことが記憶に新しい。
先兵たちの憂鬱
「生産緑地の2022年問題」とは、全生産緑地の8割(約1.1万ha)が1974年の旧生産緑地法ではなく1992年の新生産緑地法で指定を受けており、その指定期間30年が満了する2022年に一気に宅地市場に放出されて混乱が生じるとされた問題である。
これらの生産緑地とその所有者たちは課税を軽減されるのと引き換えに「生涯営農」「転用不可」といった“地縛”を受け入れ、できるだけ多くの土地を公共に服させることで80年代後半の土地バブルを鎮静化しようとした国の先兵役を務めてきた。その終わりが近づいていた。
任を解かれる彼らを待ち受けていたのが、農地評価から宅地並み評価に変わって跳ね上がる固定資産税――なにせ三大都市圏の指定都市に所有する最低500㎡以上の土地なのだ――と、連動して跳ね上がる都市計画税だった。さらにこの30年のあいだに元の所有者が亡くなっていれば、猶予されていた相続税が死亡時までさかのぼって、宅地並み評価課税で相続人にかかってくる。期限まで3年半に迫り、相続税破産が現実味をおびてきた人たちはかなり多かったのである。
都市農業に期待される新たな役割
計画の案文を読み込むと、政府、農林水産省、国土交通省がいかに都市農業に積極的な期待を寄せているかが伝わってくる。新たに都市農業に期待されている役割は次のようなものだ。
A.農産物の供給(地産地消による新鮮で安全な食料の供給)
B.防災(市街地においては延焼遮断帯や災害時避難地になる)
C.良好な景観の形成(農地を緑地の一環と位置づけ)
D.国土・環境の保全(雨水の貯留・浸透、地下水の涵養、生物多様性の保全)
E.農作業体験・学習・交流の場の提供(体験農園や学童農園、地域コミュニティ醸成)
F.農業に対する市民の理解の醸成(産業構造におけるプレゼンスの確保を恒久的に)
※「都市農業振興基本計画」と国土交通省都市局作成「生産緑地法等の改正について」をもとにアレンジ
Aについては現在でも農家戸数と販売金額で全体の9%を占めており、食糧自給の一翼を担っていると評価されている。食の安全保障を担保するためにも、消費地にある、もしくは隣接しているという好立地を活かしてより存在感を増すよう求められている。
実際に昨年、面積が500㎡未満でも自治体の条例に基づいて300㎡から指定が受けられるよう、生産緑地法の一部が改正された。三大都市圏の特定市に限らず生産緑地を増やすためである。さらに建物についても規制が緩和され、面積割合等の規定はあるものの、収穫物を使うレストランや直売店を緑地内に開けるようになった。これなどは地産地消を強力に後押しする措置だ。
Bについては、南海トラフ地震や首都直下型地震の可能性が指摘されるなかで市民の防災意識が高まっていることが背景にある。Cは昨年施行の「都市緑地法の一部を改正する法律」において、農地が緑地の一環として初めて位置付けられた。Dは現在国連が進めるSDGs(持続可能な開発目標)の目標6「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」を彷彿させる。
そしてE、Fをめぐっては、かつての農本国家からあまりに遠く離れすぎた現在の日本の姿への反省があるのかもしれない。自治体が運営する市民農園が空き区画の順番待ちなのも、企業やNPOが「特定農地貸付」制度を利用して運営する市民農園が人気なのも、社会全般で〈農〉を軸にしたコミュニティ醸成の機運がかつてなく高まっていることの証だろう。
貸借円滑化の先にある〈農〉
2022年以降は「公共に服する土地の守役」から「新たな都市農業の担い手」へと明確に役割が変わる。現所有者は期限前に登録すれば新たに「特定生産緑地指定」を受けることができ、税の軽減措置も引き継がれるが、中には疲れた者もいるだろう。相続人に営農の意思がない場合もある。であれば、都市農業に情熱を持ち積極的に任に当たってくれる人に営農を託すべきではないか――。そこで出てきたのが「都市農地の貸借の円滑化に関する法律案」だったわけだ。
今回この法律が成立したことで、これから新規の就農希望者が増えるに違いない。世代そのものの若返りも期待できるだろう。また、本格的に農家になるのではないが没頭できる趣味やレクリエーションのため日常的に〈農〉にいそしみたい人――相当数いると思われる――に向けても、適切な受け皿が提供できるようになる。始まりは「DASH村」でいいわけだ。そうやって小口の、いわばオンデマンドのニーズを集積して取り込んで成り立っていく〈農〉というものも、プロシューマーの時代の都市農業には大きな力になるのではないか。
最後に、執筆に際して読んだ農林水産省と国土交通省の資料がどれも端正な美文だったことを付け加えておく。農本思想の厚みはこんなところに生きているのかと嘆息する思いだった。
(2018.7.4)