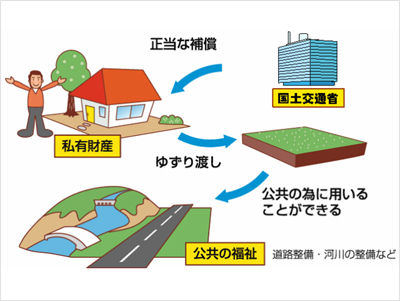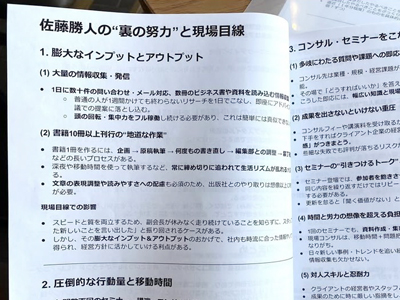バブルと呼ばれた頃

京都議定書が発効した2005年以降は特に、再生可能エネルギーの早期普及が各国とも喫緊の課題になった。日本は2004年にまとめた太陽光発電の開発・普及のためのロードマップ「PV2030」を予定より前倒しで改訂し、2009年に「PV2030+」として発表。太陽光発電の発展が「2030 年までに主要なエネルギー技術の1つに認知される」状況から「2050 年までには1次エネルギー需要の5~10%を賄う」状況に進むという想定で、太陽光発電の余剰電力に対する固定価格買取制度(FIT)を同年11月にスタートさせた。太陽光発電電力の売買そのものは以前から行われていたが、それまでは火力発電などの通常電力と同じ1kWh(キロワット・アワー)あたり24円で買われていたものが、この制度によっていきなり倍の48円で、しかも10年間固定価格保証で買ってもらえるようになったとあって各方面から参入が相次ぎ、「太陽光バブル」と呼ばれる様相を呈したものだった。
「売電」から「蓄電」へ
代わって出てくるのが「蓄電」。つまり、発電した電力を売らずに溜めておいて自分で使うスタイルへの移行だ。「溜める」という要素が相対的に弱かったのは発電設備だけでも非常に高価だったことが一番の理由だが、普及に伴い製造コストが下がり続けた結果、今やシステム導入の費用は10年前の3分の1程度と言われる。しかも技術が進んで発電性能が向上したことで、現在では、売らずに溜めておけば世帯消費分はまかなえるほどの発電能力(発電量)が基本的には確保できるようになった。※設置環境による。
そこで蓄電池が注目されるわけだが、家庭用の太陽光発電システムで蓄電池も備えたものは、まだほとんど普及していないのが現状だ。理由はまたしても非常に高価であることだが、昨年末、アメリカのテスラが長寿命・大容量・省スペースの家庭用蓄電池システム「Powerwall(パワーウォール)」を発売すると発表。価格は業界平均のほぼ3分の1という安さだった。工事費を入れても二桁万円で蓄電池システムが導入できるようになるとあって、多くの人が、太陽光発電普及の潮目が変わると印象づけられたはずだ。
「コミュニティ」への着地と経営者感覚
リサーチを続けていると、実践者たちの声とは別に、システムを販売する側やアナリストが今後の太陽光発電を分析する声も聞こえてくる。その誰もが普及のカギとして語るのは、「初期投資額が短期間で回収できること、確実に回収できること」だ。しかし、それらは、当の実践者たちの感覚と微妙にずれている気がして仕方がない。むしろ文明評論家のジェレミー・リフキンによる次の一節のほうが、当人たちも意識していないレベルの本音を言い当てているのではないか。
「前者(筆者注:資本主義市場)が財産権や買い手の危険負担、自主性の追求を促す一方、後者(同注:ソーシャルコモンズ)はオープンソースのイノベーションや透明性、コミュニティの追求を奨励する。」(NHK出版刊『限界費用ゼロ社会』p36)
引用の「財産権」は「売電目的の投資」に、「買い手の危険負担」は「初期投資が回収できること」になぞらえられるだろう。しかし、筆者が感じた太陽光発電の当人たちの実践は、むしろ後者の要素に重なる。つまり「オープンソースのイノベーションや透明性」は「世帯ごとに違うシステム構成と発電環境について情報交換し、助けあうこと」であり、「コミュニティの追求」は「クリーンエネルギーの仲間を増やし、互いに運用を競いあう楽しさ」だ。
さらに「コミュニティ」には物理空間としてのコミュニティ=「地域」という意味も重なる。政府が「災害に強い地域社会づくり」の文脈で「コミュニティ」を語る時の意味がそれだ。パナソニック製品関連の記事では、昨年4月の熊本地震の際、停電した地域で同社の蓄電システムを導入していた家庭がプチ避難所のようになり、近隣にお湯を分けるなどしながら通常の生活を送った例も報告されている。
実践者の様子を追っていると、初期投資を額面上回収したかどうかも確かに意識はするが、それはいわば経理の部分であって、それよりも本当は「エネルギーを自給自足することによる自己信頼感」や、「売電を通じて味わう経営者感覚」を楽しんでいるように思えてくる。例えるなら、10年スパンで支出する何百万円のうち5万円の回収見通しを懸念して判断を変えるのは経理事務の感覚であり、経営者の感覚とは自ずから違うものだ。そもそも買い物とは、「それが良さそうで、欲しくて、今買う余裕があるのなら買ってみる」という行為のことであるはずだ。煽るわけではないが、状況が許せば真っ先に太陽光発電を始めてみたい気がするのは、筆者だけだろうか。
(2017.8.4)