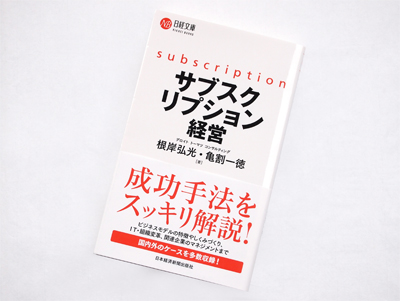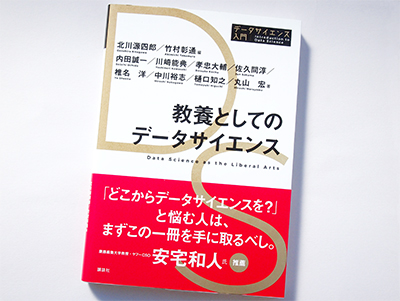本書執筆の経緯があとがきに書かれています。それによると、直接のきっかけは著者が主席研究員を務める一般財団法人アジア太平洋研究所の「中所得国の新展開」プロジェクト(2016~2018年)。著者の後藤健太氏は同プロジェクトのリサーチ・リーダーでした。「中所得国の台頭がアジア経済にどのような本質的変化をもたらし、それが日本の将来展望にいかなる意味を持つか」との問題関心で臨んだこの研究での収穫が、本書の根幹になっています。
そしてもう一つ、2018年3月に出版した『現代アジア経済論』での仕事も大きく影響したそうです。「21世紀のアジア経済を描いた新しい大学生向けの教科書」をつくるべく各大学から4名の編者が集まり、若手研究者まで含めて総勢12名でチームを組んだ編集会議は2年半の制作期間中に15回を数え、毎回“白熱ゼミ”の様相で7時間から8時間にも及んだそう。これらのエッセンスを詰め込んだからこそ、内容の濃さと新書らしい読みやすさがハイレベルで両立した一冊になったのでしょう。
ただ、この内容の濃さはたぶんこれでも入門編です。Amazonレビューで「著者の結論は別に目新しいものではない」とか「副題はちょっと大げさで、内容としても不充分」とか書かれているのは、そのあたりを指しているのだと思います。評者はこのレビューを判定・評価できるほどの学識を持ち合わせていませんが、確かに、読んでいてまったく新しい知見に啓かれるかといえば、そういうことはないかもしれません。
でも、それは逆に言うと、本書の主な内容の一つである「グローバル・バリューチェーン」が日本国内で普通に生活していても肌で感じられる状況になっているからです。日本を含んだそのバリューチェーンの存在を、日常的に意識しているからです。その意味では本書は再確認のための書だと思います。ただし、ものすごくくっきりした輪郭で、「なるほどそういうことだからそうだったのか」と、本書が対象とする各国およびそれらの国々出身の人たちへの理解を深めながら再確認できます。
そしてもう一点、なぜその「グローバル・バリューチェーン」がある種の既視感をもって受け止められるかといえば、国内の要素だけで見ても、グローバル・バリューチェーンと同型の産業構造の変化が何年も前から続いているからです。この点では本書は各国およびそれらの国々の人たちへの理解つまり他者理解をうながす書であるとともに、自己理解のための書でもあります。
自己理解と他者理解――この2つが段落を並べた箇所が178、179ページにあります。やや長くなりますが大事なのでそのまま引用します。
「高度化が果たせないと、企業としては労働条件等を下げて生き残りを図る他に道がなくなってしまう。こうしたタイプの競争戦略は、一般的に「底辺への競争(Race to the Bottom)」と呼ばれる。タイのメーソートの事例が、こういうパターンに限りなく近い。一方では先述した、自ら製品企画やデザインを担い、地場市場向けに生産・流通を主導するようなインフォーマル経済の姿が同居しているのが、アジアなのである。
まだ途上国の性格も併せ持つアジアの人々にとり、インフォーマル経済はよりよい暮らしへの有力な上昇経路となりうるが、「底辺への競争」に巻き込まれれば相対的貧困が拡大してしまう可能性もある。21世紀は確かにアジアの世紀だが、アジアの人たちの多くが、まだこうした世界で生きている。様々な制約の中で、知恵を絞って日々の糧を得ようとする、生存をかけた姿もそこにある。こうした多様で奥行きのある地域としてアジアを認識することは、現実感覚に根差したアジア経済観の醸成に不可欠である。」(第5章 もう一つのアジア経済)
前段が自己理解、つまり国内の変化を、アナロジーで理解できる箇所。後段が他者理解のための箇所です。前段の「タイのメーソート」とは、タイの輸出向けアパレル産業――労働集約的な縫製工程だけを担っていた――が「工程」「製品」「機能」のいずれでも高度化を果たせなかった結果、バンコクやその周辺から賃金の安い地方に工場が移転していき、最後はミャンマーとの国境沿いの街メーソートに集積したという話です。しかしそこで働くのはもはや賃金水準の上昇したタイ人ではなく、川を隔てた対岸のミャンマーから毎日船に乗って働きに来る労働許可証なしのミャンマー人と、ビザなしでメーソートに居住するミャンマー人でした。
これと同型のことが日本でも、外国人技能実習生や留学ビザで働きに来る外国人労働者でやっと成り立っている分野で起こっています。そして日本人の間でも、「高度人材」との対比でそういう言い方になるであろうところの低・中度人材が、派遣などいわゆる非正規雇用に集積し、国内格差が広がっています。「川を隔てた対岸」が暗喩におさまっているうちに当該分野の高度化を実現すべきです。
そして後段の引用については、「現実感覚に根差したアジア経済観の醸成に不可欠」の部分を、「現実感覚に根差した他者理解としてのアジア観の醸成に不可欠」と読み換えることができるはず。
私たちのアジア観は他者理解ベースになっているでしょうか。なっているとして、その理解は偏見やヘイトではない現実感覚に、根差しているでしょうか。自国の戦後史もまともに教えない国で――自己理解の背骨がない国で――国民に他者理解が醸成されるとは思えません。そして他者理解が醸成されないということは、自己理解において内なる他者を包摂できないということです。川の対岸を許すことができなければメンタルを病みます。メンヘラが増えるのも当然だと思います。
そのように考えると、せめて祖型なりともアジアおよびアジアの隣人たちについての他者理解を深めることは、大きな意義があると思います。本書は「経済」を切り口としてそれを助けてくれる一冊です。副題の大仰さにアレルギーを感じた人も、帯の「日本はなぜ後退したのか」のコピーに「またか」とうんざりした人も、いったんその印象は脇において、読んでみてはいかがでしょうか。