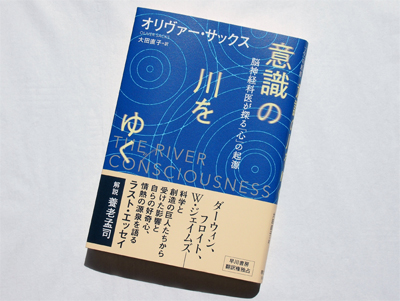もとより、医学ないし科学の知見がベースであれば専門家以外が「評」をくだすのは烏滸の沙汰(おこのさた)というもの。そちらは巻末の養老孟司氏の解説にお任せして、このレビューでは、ビジネス媒体の読者が日常へのヒントを連想できそうな箇所をいくつか抜き出して、紹介してみます。読んでいくと、ある箇所では要素の集まりから別の暗喩を受け取って、またある箇所では説明をそのまま理解して、いろんな連想が浮かぶからです。
「なぜかを問うことによって、意味(究極のものではなく、用途や目的という直接的なもの)を探り、ダーウィンは自分の植物学研究に、進化と自然選択の最強の証拠を見つけた。/ダーウィンは『種の起源』を「ひとつの長い論証」だと言った。それに引きかえ彼の植物学の著書は、もっと個人的で思い入れが強く、形式的にもそれほど系統立っておらず、その効果を論証ではなく実証によって確保している。」
(第1章「ダーウィンと花の意味」p30より中略しつつ引用。以下引用も同様)
例えば第1章のこの箇所。ここで著者は『種の起源』のアプローチ(=論証)とその後の植物学の著書のアプローチ(=実証)とを対比させているわけですが、評者はここで両者の違いを思うよりも、アマゾン社のプレゼンの話を思い出しました(BUSINESS INSIDER JAPAN「6ページの長文メモ、ベゾスも認めるアマゾンの「奇妙な会議ルール」」)。
なぜかを問う、意味を探る、個人的に思い入れる、効果を実証で示す。これ全部、企画プレゼンの必須要素ではないでしょうか。文学ではありませんから、ビジネスにおける「意味」は用途や目的でいいわけです。それらに企画者の思い入れで魂を吹き込み、実証データで脇を固め、一つの長い論証に練り上げる。ベゾスがリンク先で自社のプレゼン資料を「議論のための、コンテキスト(文脈)を作り出すためのメモ」と言ったのは、彼にとってビジネスとは、自社が社会に投げかける壮大な仮説をめぐってひとつの長い論証を試みることなのでしょうね。
「盲点や暗点を「埋める」とか、錯視を経験するというような、最も基本的なレベルでも、脳はもっともらしい仮説、パターン、あるいは光景を組み立てる。そのモデル(評者注:
(第4章「別の道――神経学者フロイト」p101)
この箇所は、人工知能を研究するコンピュータ技術者にとっては思わず膝を打つ内容ではないでしょうか。仮に技術者でなくても、ビッグデータやディープラーニングといったコンピュータ技術の概念を一般のビジネスパーソンが強い印象をともなって理解したいときに、かなり助けになりそうな気がします。人工知能研究の一方の極みが人間の脳の神経細胞の配列やそこでの電気信号をそのままコピーして人工“脳”をつくる発想に向かっている今、この箇所にある論理的な記述の含蓄と、コピーという唯物的な発想との差異を思ってみるのもおもしろそうです。
「心理学者で記憶を研究しているエリザベス・ロフタスは、架空の出来事を経験したと被験者に暗示するだけで、虚偽記憶の植えつけに怖いくらい成功したことを報告している。そうしたにせの出来事は、滑稽なものから少し動揺するようなもの(子どものときにショッピングモールで迷子になったなど)、そしてもっと深刻な事件まで、多岐にわたる。被験者はその出来事について最初は疑い(「私はショッピングモールで迷子になったことはない」)、次に自信をなくしたあと、強固な確信を持つので、実験者がそもそもその出来事は起こっていないのだと明かしたあとでさえ、植えつけられた記憶は真実だと主張し続ける場合がある。」
(第5章「記憶は誤りやすい」p123)
記憶は人間の意識にとって最大のテーマの1つ。こういった箇所からは、言った・言わないの水かけ論の不毛さを心の底から(頭の中から?)納得するとともに、文書にして残すこと、それも大事な取り交わし事項などはドラフトを相手に送って双方確認を経て文書で残すことの重要さを再認識させられます。文書化を渋る相手には「御社のためです」と言ってあげるべきでしょう。「お互いのためですから」なんて生ぬるい言い方をしていてはいけません。それでも明確な理由もなく渋るようなら、それこそお互いのあいだの信頼が迷子になる前に、そのショッピングモールから出るべきかもしれません。
最後は解説からも1節。いかにも養老孟司氏を思わせる文章です。
「若い時から感じていたことがある。イギリス人の論文は面白いが、アメリカ人の論文は詰まらない。おそらくこれは、サックスがいわば歴史を書こうとしたこととも関連するであろう。アメリカ人なら、歴史より、現状のデータをコンピュータに入れるはずである。だから物語が消え、世界はだんだん面白くなくなるのに違いない。コンピュータがヒトと置き換わるのは、ヒトがヒトであるくせに、コンピュータのようにばかり、考えようとするからである。」(p228)
AIが現代人の強迫(=脅迫?)観念になっている今、本書全体の〆でもあるこのラストのワンセンテンスは、「人間の創造性を活かそう!」というようなやさしいアドバイスが目立つなかで、「ヒトのくせに」とまず叱責から入るところが印象的です。ヒトがヒトであることへの信頼が絶対的であるがゆえに人を叱ることもできるのでしょう。皮肉と信愛を1つのロジックで表すのは、AIにはまだ難しそうですね。