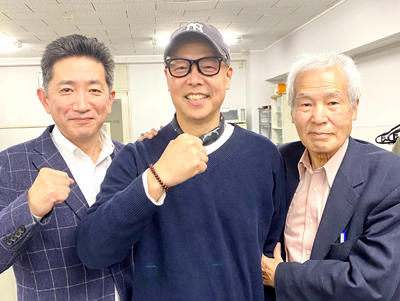楽天と京東の戦略
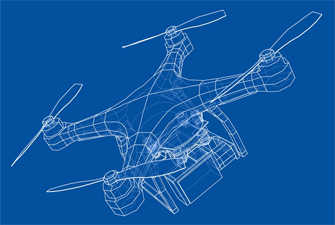
cherezoff / PIXTA
東洋経済オンラインの記事によると、京東は「無人配送の先進企業」で「実験段階の楽天から技術的な見返りが得られるとは考えにくい」が、規制が厳しく新技術の導入に慎重な日本で自社製品が採用・運用されることで、安全面その他のハードルが低い中国でいくら実績を積んでももうひとつ信用されないという問題をカバーできるメリットがあるようだ。
この報道を知って筆者は、昔聞いた航空業界のエピソードを思い出した。あくまで噂話だが、海外の航空後進国では、飛べないほどではないものの技術不足やオペレーションの余力のなさ等の理由で充分に点検・整備ができない機体は日本行き便にしてとりあえず飛ばしてしまう時代があったそうだ。復路で機体が帰ってくるときには日本の空港の離陸前点検で完璧に整備されているから、と。
京東は江蘇省や陝西省等の中国農村部で40万分以上の配達飛行実績を持っている。楽天は国内市場における「ドローンによる無人配送」のリーダーの地位を早く固めたい。実証研究のフェーズではドローンの自律制御技術で国内トップとされる株式会社自律制御システム研究所と組んできた楽天だが(機体名「天空」)、事業フェーズでは“実績”という既成事実で厳しい規制をこじ開ける戦略に出たのだろうか。
一気に来た潮目
そもそもドローン――正式にはUAV(Unmanned Air Vehicle=無人航空機)、または日本ドローンコンソーシアム会長で自律制御システム研究所創業者の野波健蔵氏によれば「飛行ロボット」――は国の戦略産業であり、経済産業省の「空の産業革命に向けたロードマップ2018」を見ると、今年2019年度で一定の完成を見る、あるいは新たなフェーズに入る予定が目白押しだ。
「ロードマップ」資料の3枚目「インフラ維持管理」領域では、「橋梁、送電線のインフラ点検」への利活用を2018年半ばまでにクリアし、2019年度中に「目視外飛行による長大なインフラの点検」に移り、2020年以降は「都市部(有人地帯)のインフラ点検」に進むと見込んでいる。またNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)によると、高度成長期以降に整備された社会インフラの長寿命化が現在喫緊の課題になっており、それらの整備・点検業務にロボットや無人航空機を活用することで、建設現場のベテラン人材の不足を補いつつ効率的に整備・点検ができるようになる(リンク先資料)。
先月は日立システムズが、JICA(国際協力機構)がフィリピンで行ったドローンによる橋梁点検の実証実験に参画。高所で点検通路もなく作業が困難だった橋梁に対し、ドローンで大量の2次元画像を撮影して構造物全体の3次元モデルを生成し、AIでクラックを検知・解析した(3月13日「日刊工業新聞」)。また同月、東北大学の大野和則准教授らがドローンに搭載可能な小型打音検査装置を民間企業と開発(3月6日・同)。6月からのKDDIの「スマートドローンソリューション」は従来は人力で数時間かかった鉄塔点検を60分以内に完了でき、風力発電機にいたっては所要8時間だった作業を約1時間で済ませるという。今月頭にはNTT西日本も、新会社の設立は8年ぶりという、ドローンによるインフラ点検事業の子会社を設立。営業を開始した。これらを踏まえると「潮目が一気に来た」との表現はあながち誇張ではないだろう。
人間の目、マシンの“目”
例えば同資料の「インフラ維持管理」領域の「技術開発」の欄では、2018年半ばまでに「点検箇所の高精細画像取得技術の開発」が完了することになっている。民生分野では現在8K映像が、「4Kでも目にきついのに、ここまで高精細な画像を視聴者は求めているのか」との一部の疑問の声にさらされているが、画像の高精細化はもはや人間の視聴者が見るためよりマシンの“目”が拡大編集・加工して見るために進むと思ったほうがいいだろう。資料の「インフラ維持管理」領域の次の「測量」領域に「レーザー測量」「ハイパースペクトルカメラ」といった単語が並ぶのと同じである。
また、資料2枚目「災害対応」領域の「技術開発」欄に「過酷環境(強風、降雨、降雪、噴火した火山等)に耐える機体の開発」とあるのも、人間の目が無力な環境で、人間の目には不可能なアングルで、人間には見えない光を見る“目”を行使するためである。橋の裏をのぞきに行くなどは序の口なのだ。
大脳で飛ぶドローン
メーカーの製造工程に人間の手でやる作業がまだ残っているのは(例;水産加工場)、一般に思われているように“手”の問題ではなく、実は“目”の問題なのだそうだ。人間の手の複雑な動きを代替するロボットは今までもつくれたが、目がなかった。その物体が何であるか――何という実体概念に相当するものか――を理解して接することができなかった。それがAIとディープラーニングによって可能になった。これは産業ロボットが“目”を持ち始めたということであり、古生代カンブリア紀に三葉虫などの目を持った動物が誕生して生物の多様性が一気に広がったのと同じ現象――「カンブリア爆発」――が、これから産業ロボットの世界で起きる、ということだった。
先の野波氏によれば、現在のドローンはまだ小脳で飛んでいるそうである。運動神経と平衡感覚を使ってプログラム通りに飛ぶだけで、目標値から自分で最短ルートを設計したり、途中で不調を感じたら自分で公園を見つけて不時着して助け(=JAF?)を待ったりできない。つまり大脳で飛んでいない。次世代ドローンはこれが可能になるというが、ここでもキーファクターは“目”だろう。目で見て手を動かすことを覚えて大脳が発達した飛行ロボットが考えながら空を行き交うようになるドローンのカンブリア紀は、いつ来るだろうか。
(ライター 筒井秀礼)
(2019.4.3)