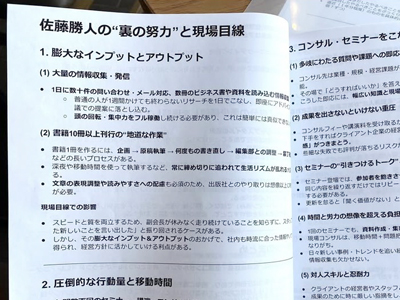改正相続税法、施行前夜
~事業者とユーザーの協働で「“終”の哲学」確立を~
◆孤立する「終」の事情と新たな問題
ただ、こういった終活ビジネスの中に、ユーザーの本質的なニーズにまで手が届くものはまだまだ少ない。
近年、「終」の現場で真の問題となっているのは、社会全体の猛烈な高齢化と、それに伴う孤立化である。特に、介護を担い、相続を受ける側の「子」がすでに老いているケースの増加が種々の問題を深刻化している。「子」が先に認知症を患ったり、介護が必要になったり、あるいは死んでしまったりするケースは、もはやレアではないのだ。
「空き家の増加」はそれにより悪化している問題の一つである。相続人全員の同意がなければ相続は成立しないが、高齢化した相続人の中に認知症の人がいると、「同意する」という法律行為が不可能になる。すると成年後見などの手続きが必要となり、膨大な時間と手間がかかる。結果、放置された家が「空き家」となるのだ。2014年7月に発表された総務省の住宅・土地統計調査によると、2013年10月1日時点での空き家数は820万戸で、住宅総数に占める割合は13.5%に達した。「7軒に1軒が空き家」という異常事態だが、対策のないまま「老々相続」が増えればさらに拍車がかかると指摘されている。
◆新たな社会哲学の構築とビジネス
「終」の局面は、空き家の増加など公の社会問題と関係しつつ、個人の命題でもある。ただ、死と向き合うことへの不安や気後れもあり、真の意味で対策をとっている人は少ない。
妨げとなっている負の感情を乗り越えるためには、「“終”の哲学」が必須だ。多くの国では宗教がその役割を果たしているが、米シンクタンク「ピュー・リサーチセンター(Pew Research Center)」の発表によると、日本人の無宗教率(57%)は世界第4位で、共産主義国の中国(52.2%)よりも高い。我々日本人は宗教に頼らず、自分で学び考えて、心棒となる理念を見つける必要があるのだ。
何を基盤とするか・・・人それぞれの考え方があって当然だが、「後世に何かを残す」というコンセプトは大きなカギの一つになる。そのベースは「文化の発祥は葬送にある」とする考えだ。「自分もいずれ死にゆくもの」という認識を手に入れたことから、人は何かを残そうとするようになった。その積み重ねが豊かな文化となり、後世の人々を潤してきた。この営みに加わることで、人の生は大きな意味を持つ。
建築家の建築物、学者の研究成果、芸術家の作品――そういったもの以外にも、平易な言葉や日常の映像など、“残せるもの・残す価値があるもの”はどんな人も持っている。現状ではそれらを「効率的に残す手助け」にとどまる終活ビジネスが大半だが、サービスを提供する側がもう一歩踏み込み、受ける側と一緒に「“終”の哲学」を確立できるなら、状況は変わるだろう。「何かを残すことは、後世の社会を益することにより個人の存在意義を確立する行為」という認識をサービス提供者と利用者が共有するのだ。それにより「終」の局面にある人たちが、よりしっかりと心根を定めることができるなら、終活ビジネスは社会的な意味を持つ。
一休禅師は髑髏を掲げることで、終わり方への意識を喚起しようとした。国家にその意図があるとは思えないが、改正相続税法の施行を財務省の掲げる「髑髏」と受け取れば、年初の一里塚に終活を思うための準備をしておくことで、「終」と向き合う哲学が見えてきそうだ。
(ライター 谷垣吉彦)